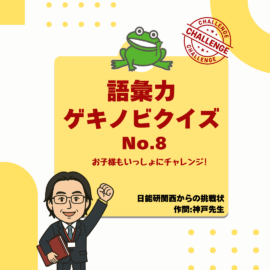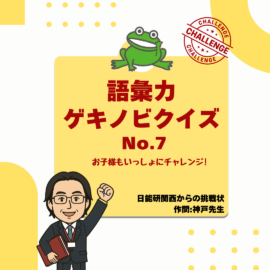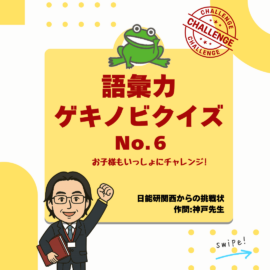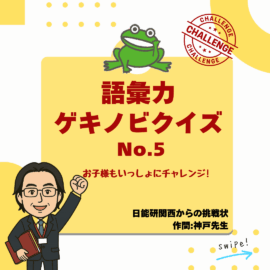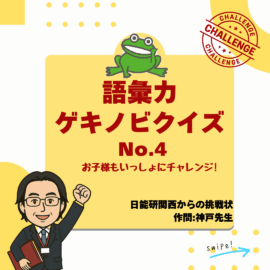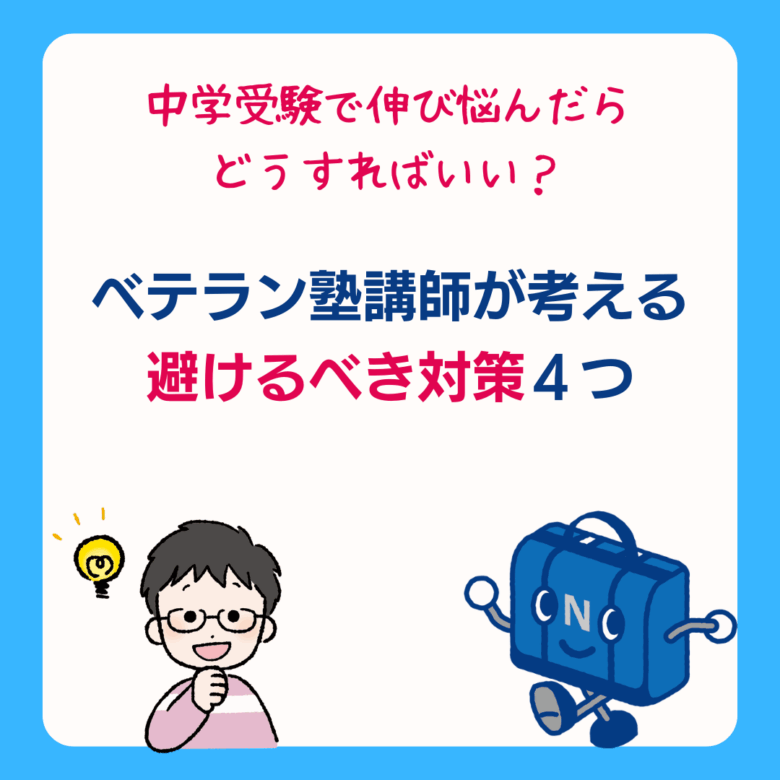
「本人なりに頑張っているのに、塾内の順位や偏差値はいつもほぼ同じ」とお悩みではありませんか。中学受験をしているご家庭では、お子さまの成績が伸び悩んでいると感じる保護者の方が少なくありません。日能研のベテラン講師である荒賀先生と邨田先生に意見をうかがい、逆効果になりかねない避けるべき対策をお聞きしました。
そもそも全員の成績アップは不可能。現状維持は学力がついている証拠
模試を何度受けても偏差値があまり変わらず、横ばい状態であることに不安を感じる保護者の方が多いようです。荒賀先生はどのようにお考えですか。
荒賀先生「学力と成績は混同されやすいですが、大きく異なります。成績は他のお子さまと比較して出される相対的なものであるため、全員の成績アップは理論上不可能です。一方、学力は絶対的なものなので、周囲に関係なく本人の努力次第で上がります。つまり、学力は全員上げられますが、全員の成績を上げることはできません」
では、偏差値が横ばいであっても、伸び悩んでいるという判断しないほうがよいのでしょうか。
「現状維持できているお子さまに対して、『伸び悩んでいる』と解釈される保護者の方は少なくありません。しかし、周囲の子どもたちが学力をつけているなかで成績を維持できているなら、学力がついている証拠です。決して伸び悩んでいるわけではありません。別の言い方をすれば、偏差値が上がった場合は、周囲も学力をつけていくなかで、より伸びている証といえます」
では、偏差値が横ばいであっても気にせず、順調に学力がついている状態だと捉えてよいでしょうか。
「塾に通って勉強している子どもたちは、基本的に学力がついています。成績は周りに左右されるものなので、そこに一喜一憂してもどうしようもありません。現状維持できているならとくに対策する必要はないでしょう。それよりも、やってはいけないことを意識していただきたいです」
成績を必要以上に悲観してご家庭で独自の対策をとると、逆効果になるケースが少なくないといいます。次回からは、成績アップを目指す保護者の方が、避けるべき対策を4回に分けてご紹介します。
NG1. 塾の数を増やす
〜課金と成績は比例しない!『増やす』ではなく「消化」を重視しよう〜
成績アップを目指す保護者の方が、もっとも避けるべき対策は何でしょうか。邨田先生が答えます。
邨田先生「塾の数を増やすことです。2つ目の塾に通う方がいらっしゃいますが、お子さまにとって大きな負担になってしまいます。『増やす』という発想から対策を講じるのは控えたほうがよいでしょう。学力は課金すればするほどつくものではなく、課金と成績は比例しません」
課金したほうがいいケースとしないほうがいいケースがあるのでしょうか。また、どのように判断すればよいでしょうか。
邨田先生「今やっていることに余裕が出てきて、物足りなさを感じている場合は、増やす対策が適しています。通っている塾のオプションにある、今よりレベルの高い講座にチャレンジすると効果的です。課金しないほうがいいケースは、消化不良になっている場合です」
消化不良とはどのような状況でしょうか。また、どのような対策をとればよいのでしょうか。
邨田先生「授業で習っていて、宿題で類題を解いていても間違える場合は、きちんと消化できていない状態です。1週間のスケジューリングを見直して、消化不良になっているところがあれば、そこを消化するために極力無駄を省きましょう。今通っている塾のカリキュラムをしっかり回すことを重視して、やることを絞っていくことが大切です」
NG2.勉強量を増やす
〜勉強は筋トレと同じくやりすぎ注意!安易な増加はケガのもと〜
親としては、勉強量を増やすと安心する部分があるように思いますが、先生はどのように思われますか。
荒賀先生「勉強量が多いほど安心感を得られる保護者の方は多いように感じます。量を増やすと『うちの子はこれだけやっているから大丈夫』と思えるかもしれませんが、筋トレと同様にやりすぎたらケガをします。量が多ければ効果が出るというものではありません」
保護者の方からの申し出で宿題や課題を増やした場合の事例について、荒賀先生が語ります。
荒賀先生「指導者側からすれば、量を増やすのは一番簡単な方法です。一つひとつが完璧にできているかを無視して量だけ与えるのであれば、何も難しくありません。実際に、宿題の増加を懇願され、逆効果になる旨をお伝えしたうえで増やした場合でも、『先生無理でした。ごめんなさい』と返却されるケースが多くあります」
自分の判断が原因で子どもに不要な負担をかけてしまうと、落ち込む保護者の方も少なくなさそうです。荒賀先生はどのように思われますか。
荒賀先生「保護者の方に実感していただけたのであれば、それもよい経験だと思います。中学受験は保護者の方も含めて、試行錯誤して進めていく受験です。そういう意味でも、『中学受験は親子の受験』と感じますね」
NG3. ネットの情報を鵜呑みにする
〜不安を煽られて逆効果になることも。信頼できる人間は一人に絞ろう〜
成績アップを叶えるために、インターネットで情報収集や相談をする方もいらっしゃるようです。
荒賀先生「信頼できる人間を一人決めたら、その人についていくことが大切です。複数の人に情報を求めると、言われることが全く違う可能性があり、不安がより一層強まる原因になり得ます」
信頼できる人というのは、やはり塾の先生でしょうか。
荒賀先生「お子さまのことをよく知っているのは、担当している塾講師です。お子さまの学力や性格、ご家庭のことを理解していない人間に尋ねても、適切なアドバイスは得難いでしょう」
インターネット上には、SNSなどで情報発信をしている塾講師も多く見かけます。有識者の意見でも信じないほうがよいのでしょうか。
荒賀先生「中学受験の業界には、残念ながら不安を煽って誘導する業者もいます。たとえ塾講師など有識者のアカウントであっても、インターネットの情報や書き込みを鵜呑みにするのは厳禁です。どこの誰が書いているか分からない情報を信じるのは、とても危険なことだと思います」
インターネットの情報はすべて信じないほうがよいのでしょうか。信頼性の高い情報かどうかの見極めポイントはありませんか。
荒賀先生「署名記事であるかどうかを確認してください。信頼に足る人物が発信しているかどうかを見極めるポイントになります。注意したいのは、いわゆるインターネット掲示板など匿名性の高いサイトに書かれた噂のような情報です」
NG4. 成績の不安を本人にぶつける
〜中学受験は成績を上げにくい世界。努力の承認が成長のカギに〜
成績アップを目指すからこそ、お子さまが伸び悩んでいると感じてしまうと、不安が募る方も多いでしょう。しかし、邨田先生によると、不安の取り扱いには注意が必要だそうです。
邨田先生「伸び悩んでいるという評価をお子さまにぶつけているとしたら、お子さまにとって不幸なことだと思います。たとえ保護者の方の期待値と比較して伸び悩んでいると感じたとしても、それをお子さまに直接ぶつけないのはとても大切なことです」
中学受験はそもそも成績が非常に上がりにくい受験だといいます。
「高校受験であれば、塾に通って少し勉強すれば、誰でも数字が上がります。勉強を全然しない子が一定数いるため相対的に数字が上がり、伸びている実感を持ちやすいでしょう。一方、中学受験は限られた子だけがする受験であり、本人の意思があるだけでなく、保護者の方のサポートも入った状態です。相対的に数字を上げにくく、成績を上げるのは非常に大変だといえます」
中学受験をしている子は、日々の勉強だけでも十分に頑張っていることを保護者の方が認めてあげる必要があるそうです。
邨田先生「偏差値がもし1ポイントも上がっていないとしても、決して伸び悩んでいるわけではありません。みんなが努力をしているなかできちんと現状維持ができているということは、確実に合格に向かって近づいているということです。努力をきちんと承認してあげて、お子さまがなるべく気持ちよく続けられる環境を整えてあげてください」
子どもが親に自分の努力を認められていることを実感しながら心地よく勉強を継続できると、成績アップにもつながっていくといいます。
邨田先生「短期的にみると数字はそれほど伸びないかもしれませんが、努力を継続していくことでお子さまのなかできちんと整理がついたときに飛躍的に成長するケースもあります。今の数字に不安があるときは、お子さまでなく我々指導者に遠慮なくぶつけてください」
中学受験は子どもだけでなく親も試行錯誤を重ねて成長する受験です。よかれと思って取り入れた対策が、悪循環を生んでしまうことも少なくありません。迷ったときこそ信頼できる先生に相談し、お子さまやご家庭に合ったアドバイスを受けることが大切です。
日能研では、お子さまや保護者の方一人ひとりに寄り添った指導や面会を行っています。お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
聞き手・文:古賀令奈