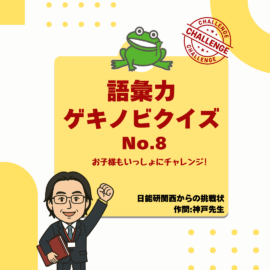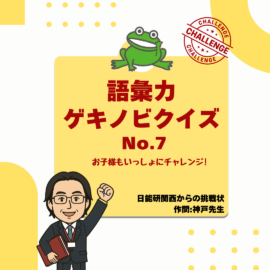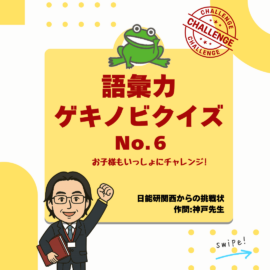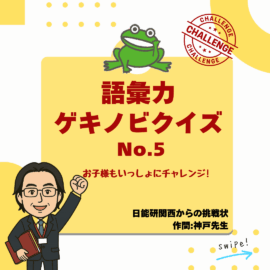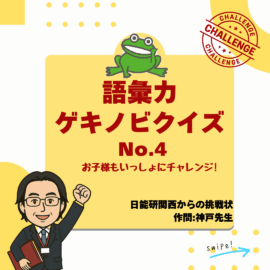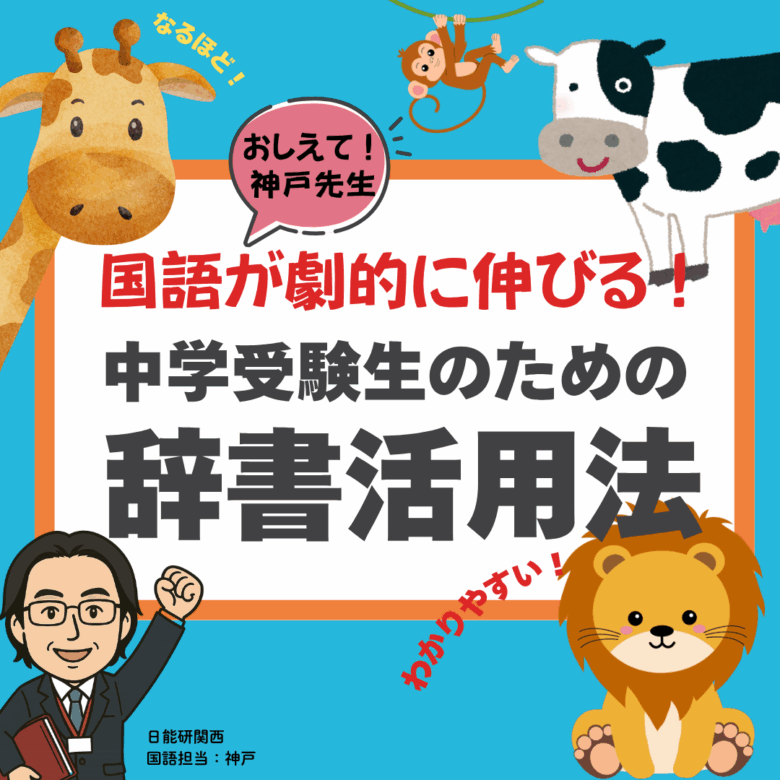
「国語の成績が伸び悩んでいる」
「何から手をつければいいか分からない」――
そんな悩みをかかえている方へ。国語力の土台となるのは「語彙力」です。
このコラムでは、語彙力を劇的に伸ばすための辞書の選び方と、その活用法を紹介します。
楽しく、主体的に学び、国語の力を伸ばしていきましょう。
小学生向けの国語辞典を「深掘り」する
国まずご紹介するのは小学生用国語辞典の『例解学習国語辞典』(小学館)です。
この辞書で、ある言葉を調べると漢字の横に小さな数字や記号が書かれています。
例えば数字の5は5年生で学習する漢字、記号の▽は「小学校では学習しない、常用漢字」という意味です。この数字や記号を学習に利用しましょう。
たとえば4年生の子なら、5という数字を見て、「まだ書けなくてもいいか。」と思うのではなく、
「5年生の漢字だけれど、そんなに難しくないし、今おぼえてしまおう。」と考えてほしいのです。
もちろん、▽の記号がついた漢字も覚えてしまっていいのです。
そして、「すごい、もう5年生の漢字や、小学校で習わない漢字まで書けるようになったぞ。」と
自画自賛しましょう。
勉強で自画自賛は大切です。
中学受験を見据えた「もう一冊」の辞書
中学入試を視野に入れると、小学生用の国語辞典では物足りなくなることがあります。そこで登場するのが「中学生用の国語辞典」です。『例解新国語辞典』(三省堂)をご紹介いたします。
たとえば、「おためごかし」という言葉が中学入試で出題されたのですが、この言葉は小学生用の国語辞典にはのっていません。でも、中学生用の『例解新国語辞典』にはあるのです。
小学生の日常生活ではまず使われないが、読書などを通して語彙力を高めた小学生は知っているという言葉はたくさんあります。中学入試ではこのような言葉(小学生用の国語辞典にはのっていないが、中学生用の国語辞典にはある言葉)も多く出題されますので、中学入試受験生には『例解新国語辞典』を強くおすすめします。
熟語の「構造」を読み解く漢和辞典
次に紹介するのは「漢和辞典」です。『例解小学漢字辞典』(三省堂)がおすすめです。
おすすめポイントは記号を使って熟語の組み立てを示しているところです。
たとえば「読書」であれば「↑」という記号がついています。「↑」は二字熟語を縦書きしたとき
に「書を読む」のように下から上にかえって読むと、意味がはっきりする熟語であることを示し
ています。
二字熟語をなんとなく暗記するのではなく、組み立てを意識しながら覚えると意味もよくわかり、
記憶が定着します。
「言葉のつながり」で語彙力を育むユニークな辞書
最後にご紹介するのは『フレーズで覚える ことばの結びつき辞典』(学研)です。
ある言葉と強く結びつく言葉にどんなものがあるかを詳しく教えてくれます。
例えば、「追随」を調べれば、「許さない」がのっています。たしかに「追随を許さない」といういい方はよく耳にしますね。
語彙力があるということは、単語を知っているだけではなく、言葉の結びつきまで頭に入っている、ということです。
この辞書を使いながら、多くの言葉の結びつきを習得すれば、語彙力は飛躍的についていきます。
保護者の方がある言葉を言って、お子様が結びつく言葉を答える、というようなゲームも楽しめますね。
以上、4冊の辞書を紹介いたしました。強制されていやいや辞書を引くのではなく、積極的に、楽しく辞書とつきあいましょう。国語の勉強がおもしろくなり、得点力も飛躍的に伸びていくこと間違いありません。
このコラムの内容は動画でも解説しています。
もっと知りたい方はこちらの動画をごらんください。