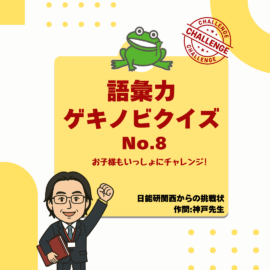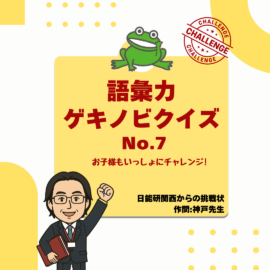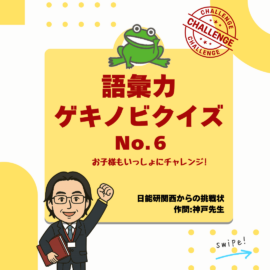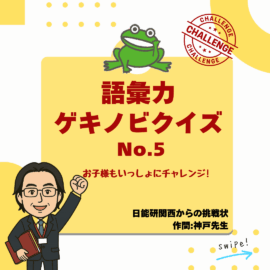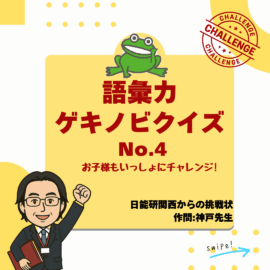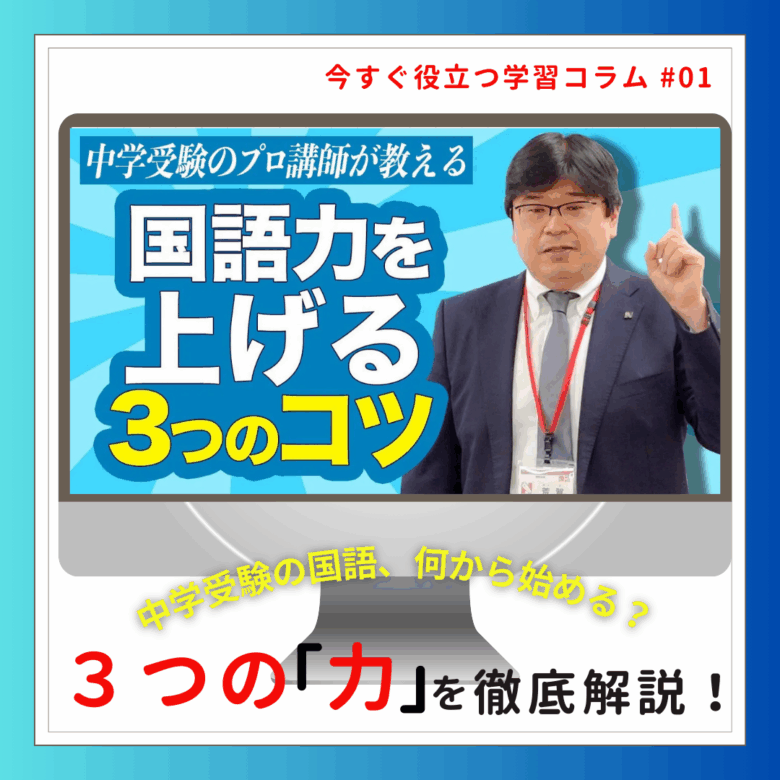
中学受験において、「国語力」は合否を大きく左右する重要な要素です。しかし、「国語力」と一口に言っても、具体的に何をどう伸ばせば良いのか、漠然とした疑問を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな「国語力」を深掘りし、合格への道を切り開くための具体的な三つの柱について、専門家の視点からご紹介します。
「国語力」とは、どんな力?
「国語力を身に付ければ、国語の問題が解けるようになる」。これはもちろん当然のことですが、その「国語力」という言葉の具体的な中身については、意外と知られていません。まずは、中学受験の「国語力」を構成する要素を紐解き、お子さんの力を効果的に伸ばすヒントをお伝えします。
国語力は、大きく分けて次の三つの柱から成り立っています。
1.言葉の知識:語彙力や漢字、ことわざなどの知識。
2.読解力:文章の内容を正確に読み解く力。
3.表現力:読み取った内容を自分の言葉で的確に伝える力。
これら三つの力がバランス良く備わってこそ、真の「国語力」が身につくと言えるでしょう。
まずは土台から!「言葉の知識」を深めよう
国語の力を育む上で、最も基本的な土台となるのが「言葉の知識」、つまり語彙力です。文章が日本語で書かれているとはいえ、使われている言葉の意味が分からなければ、書かれている内容を理解することはできません。豊富な語彙力こそが、国語の学習における最も重要な基盤であり、読解力を養うための出発点となるのです。
中学受験における「言葉の知識」は、主に二つの系統に分けられます。
・知識問題として問われる言葉の知識: これは、ことわざ、慣用句、四字熟語といった、いわゆる「知っているか知らないか」が問われる問題です。関西圏の中学入試では、国語の問題全体の約20%から25%を占めることもあります。これらをしっかり覚えることで点数を確実に稼ぐことができます。
・一般的な語彙力: 文章の中で使われている言葉の意味を正確に、どれだけたくさん知っているか、という力です。こちらは直接的な知識問題として出題されるというよりも、文章全体を理解するために必要となります。文章を読む上で言葉の意味が曖昧だと、重要な部分を深く理解することができません。
論理の探偵になろう!「読解力」の磨き方
言葉の意味がしっかり理解できるようになったからといって、文章の内容を正しく読み取れるかというと、それはまた別の話です。ここで必要となるのが、「読み解く力」、すなわち「読解力」です。読解力とは、文章を「論理的に」読むことを指します。
論理的に文章を読み解くためには、主に三つの関係性を意識することが大切です。
1.類比関係(イコールの関係): 筆者が伝えたい核となる主張を、様々な形で言い換えている部分を見抜く力です。例えば、筆者は自分の意見を一度述べるだけでなく、相手を説得するために、以下のような方法で同じ内容を繰り返したり、別の角度から説明したりします。
・具体的な例を挙げて説明する。
・分かりやすい比喩や例え話を用いる。
・他の著者の言葉を引用して、説得力を増す。
これらの「イコールの関係」を見抜くことで、筆者の最も言いたいことを深く理解できます。
2.対比関係(反対の関係): 二つの物事を比較し、その「違い」を読み解くことで、筆者の主張や意図を明らかにする力です。例えば、入試問題では、異なる文化(日本の文化と欧米の文化など)を比較したり、現代と過去(現代社会と江戸時代など)を対比させたりして、それぞれの特徴や変化を説明する文章が多く見られます。反対の関係にある要素を整理しながら読むことで、筆者が伝えたいことが見えてきます。
3.因果関係(原因と結果の関係): 物事の「原因」と「結果」の関係性を把握する力です。筆者は、ある主張をする際に、必ずその理由や根拠を伴って説明します。私たち文章を読む側も、「なぜこうなったのか」という因果関係を整理しながら追っていくことで、文章の流れや筆者の論理展開を正しく理解できます。
これらの論理的な関係性を見抜く力と、土台となる言葉の知識は、車の「両輪」のようなものです。どちらか一方だけでは、文章を深く理解することはできません。正確な言葉の知識を豊富に持ち、これら3つの論理を意識しながら文章を読み、正しく内容を理解していく力が「読解力」と言えます。
読み解いた内容を伝える「表現力」
言葉の知識と読解力をしっかり身につけ、文章の内容を正確に理解できるようになったら、次に重要になるのが「表現力」です。特に、最難関校の入試問題では、読み取った内容を自分の言葉で答える「記述式」の問題が多数出題されます。
国語の入試問題の出題形式は、主に三つあります。
・選択式:複数の選択肢の中から正解を選ぶタイプ。
・抜き出し式:文章中の適切な部分を探して抜き出して答えるタイプ。
・記述式:問われた内容を自分の言葉でまとめて答えるタイプ。
選択式問題は、曖昧にしか理解できていなくても、選択肢を頼りに正解を選べることがあります。しかし、記述式問題では、「書けなければ点数に結びつかない」という厳しい現実があります。どれほど文章を正確に理解できていても、それを「相手に伝わる日本語」で表現できなければ、得点にはつながりません。
この「表現力」は、特に小学5年生、6年生になってからの学習で重要度が増してきます。読み取った内容を明確かつ論理的に、そして簡潔にまとめ上げる技術を身につけることが、中学受験を突破する鍵となります。
まとめ:国語力は「3つの力」の調和から生まれる
中学受験における「国語力」は、単なる暗記や感覚で身につくものではなく、「言葉の知識」「読解力」「表現力」という三つの要素から成る総合的な力です。
・まずは語彙力を豊かにし土台を固める。
・次に論理的な読み方で文章の構造を把握する。
・そして、その理解を自分の言葉で表現する練習を重ねる。
この一連のステップを通じて、お子さんの「国語力」は着実に向上していきます。今回ご紹介したポイントを意識して学習に取り組むことで、きっとお子さんは自信を持って中学受験に挑めるようになるでしょう。これからも様々な学習のポイントをお伝えしていきますので、ぜひご期待ください!
このコラムの内容は動画でも解説しています。
もっと知りたい方はこちらの動画をごらんください。