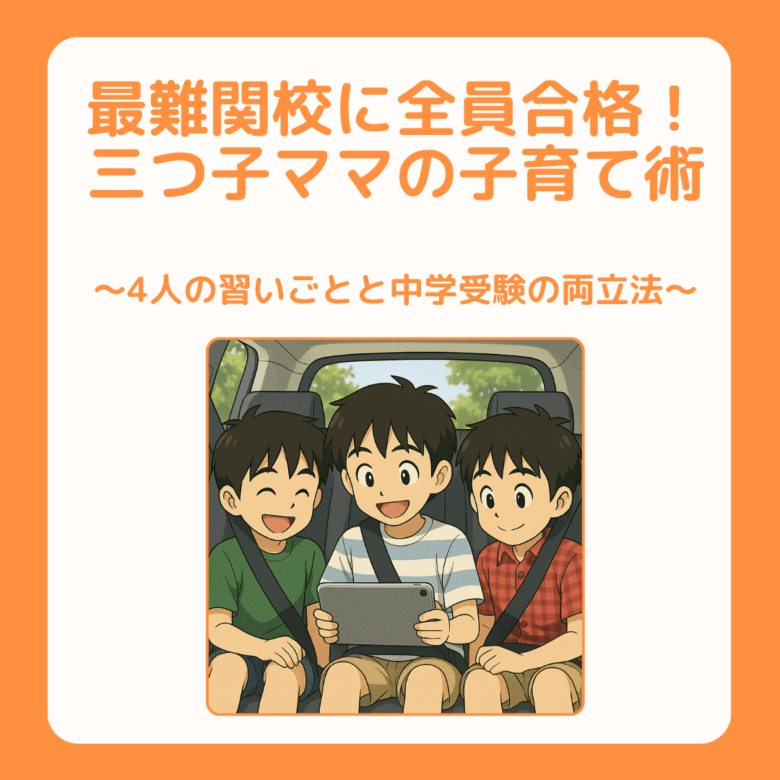
最難関校に合格する子どもといえば、幼少期から勉強一色の生活で育ってきたと思われるかもしれません。しかし、三つ子全員が甲陽学院中学に合格したOさん一家では、子どもたちのやりたいことを尊重し、習いごとを楽しみながら中学受験に励んでいたといいます。
今回は、三つ子ママのOさんに、お子様たちの習いごとと中学受験の両立法をお聞きしました。
年中から入塾までの勉強は公文。国語を最重視していた
日能研に入る前までの三つ子くんたちは、学校の宿題以外の勉強を何かしていましたか。
「幼稚園の年中から日能研に入る4年生までは、公文に通っていました。国語を選びましたが、2年生の終盤〜3年生序盤あたりに漢字検定5級(小学校6年生修了程度のレベル)を取得したので、それを節目に科目を変更しています。中学校で習う古文や漢文などまで手を広げるよりも、他の科目に変えたほうがいいかなと思ったからです」
科目は何に変更されましたか。また、変更による効果はいかがでしたか。
「三つ子のうち2人は算数、1人は英語に変更しました。ただ、あまり活かされた印象はありません。計算が早いわけでもなく、英語を今も覚えているわけでもなかったです。とくに英語は、中学受験塾に入るまでのつなぎという感じでした」
長く続けた国語には、効果を感じた部分はありましたか。
「国語がすごく得意というわけではありませんが、4〜5年生ごろは国語の成績がよかったので、序盤は役に立った印象です。甲陽学院の国語は記述問題が多いこともあり、公文での下積みが活かされていたように感じます」
習いごとの送迎は4人分。全員違う習いごとの日はずっと送迎
三つ子くんたち全員が塾や習いごとに通うとなると、お母さまのご負担は大きいかと思います。何か工夫はされていましたか。
「三つ子の下に長女がいるので、4人の送迎となると大変です。送り迎えの回数を抑えるためにも、できるだけ4人とも同じところに通わせたいのが本音でした。そして、実際に公文とスイミングは全員同じところに通えました。三つ子と下の子では時間が違うので、送迎が一度で済むわけではありませんが」
他の習いごとはそれぞれ違ったのでしょうか。
「三つ子でも2〜3年生になると興味や趣味が変わってきます。習いごともそれぞれ自分で選ぶので、バスケットボール・バドミントン・将棋と3人バラバラになりました」
行き先もそれぞれ異なり大変だったかと思いますが、お母さま一人で全員の送迎をこなしていたのでしょうか。
「車でそれぞれ駅や教室まで送っていました。月曜日は4人全員習いごとが違っていたので、ずっと送ってばかりで大変でしたね。でも、彼らのやりたいことはできるだけ続けさせてあげたかったので、よかったと思っています」
練習なしの習いごとは受験ギリギリまで継続。リフレッシュに効果的
2〜3年生ごろから三つ子くんたちそれぞれが好きな習いごとを始めたとのことですが、いつ頃まで続けていらっしゃいましたか。
「長男はバスケを6年生の12月まで、三男は12月の冬季講習に入る直前まで将棋を続けていました。二人はギリギリまで通っていましたが、そのおかげで受験本番が迫る時期でもリフレッシュできていたようです」
追い込みの時期に受験勉強と並行して習いごとに通うのは大変ではありませんでしたか。
「将棋はチケット制で好きなときに行けるので、宿題に余裕があるときに行っていました。バスケも将棋もその場でするだけなので、自宅で練習に時間を割くことはありません。ピアノのように家で練習をしてレッスンでみてもらうスタイルだと難しかったと思います。ただ、練習をしないから上達もしないものの、気分転換になっていたようです。習いごとのあとは普段と比べて勉強がはかどっていました」
受験終盤で楽しめる余裕があるのは素晴らしいことですね。
「三男は将棋をしていたので、相手とおしゃべりできるのもよかったのかもしれません。先生も対局相手も大人だから同年代からは聞けない話ができて、聞いている私も楽しかったですね」
子どもたちのやりたいことを尊重する姿勢が、子どものやる気を育てる鍵
最難関校の中学受験というと勉強一色の生活と思われがちですが、趣味やスポーツでリフレッシュしながら受験生活を楽しんでいたというお話が印象的でした。
Oさんのように子どもたちがやりたいことを尊重し、できる限り継続できるようにサポートする姿勢が、子どものやる気を育てる鍵なのかもしれません。
日能研では、三つ子くんたちのように毎日を豊かに過ごす受験生活を応援しています。自分らしい中学受験を目指したい方は、ぜひ日能研にご相談ください。
聞き手・文:古賀令奈





