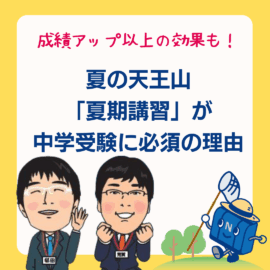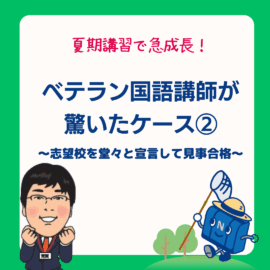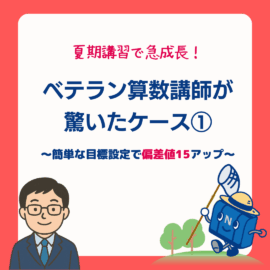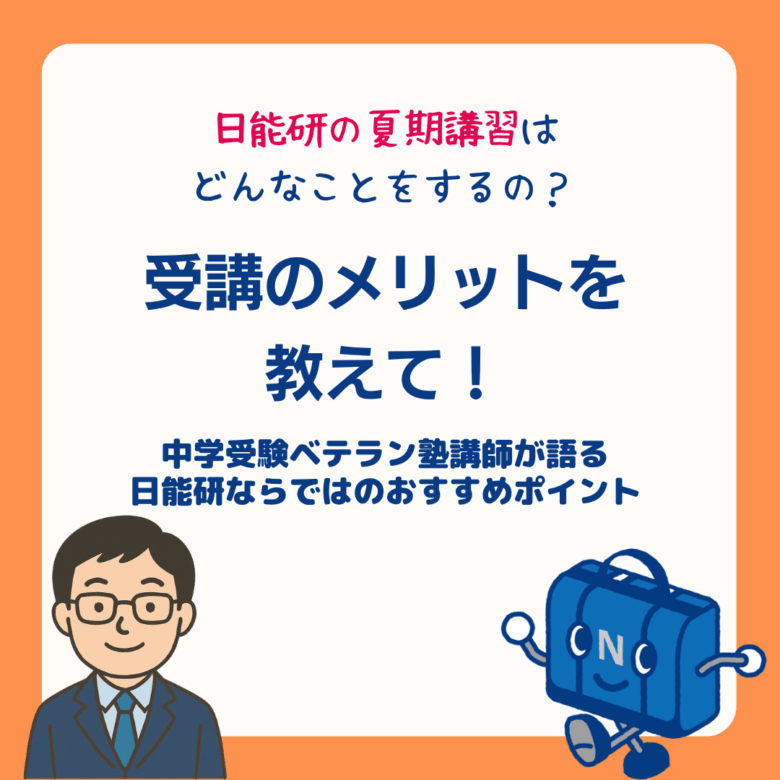
受験生の夏といえば夏期講習。夏休み期間は各塾で夏期講習が開催されますが、塾によってカリキュラムや取り組み方が異なります。そこで今回は、ベテラン講師である荒賀先生と邨田先生に、日能研の夏期講習の特色をうかがいました。日能研ならではのメリットは必見! 夏期講習の受講にお悩みの方は、ぜひご覧ください。
通常授業なし。おさらい特化で基礎学力の定着を図る
日能研では、夏期講習の期間中に通常授業が行われるのでしょうか。算数の邨田先生が答えます。
「通常授業は行いません。日能研は夏期講習を挟んで前期・後期に分かれており、夏期講習では前期のおさらいの授業を行います。通常のカリキュラムをストップしておさらいに特化するため、新しいことはしません」
邨田先生によると、普段は他塾に通っているお子様、まだ日能研に通っていないお子様も、夏期講習によってさまざまなメリットが期待できるといいます
「塾生が前期に取り組んできたことを夏期講習で振り返るので、後期からの受講を検討しているお子様もスムーズに入りやすくなるでしょう。後期からの入塾を検討しているご家庭には、夏期講習からの受講をおすすめしています」
夏は自宅学習を優先して夏期講習を受けないご家庭もごく一部あるようですが、夏期講習はすべてのお子様に必須といえるほど重要だそうです。
「普段の授業では新しいことが次々に出るため、すべてを網羅するのは難しいでしょう。しかし、前期の内容を網羅するので、未消化な部分や苦手分野を克服する絶好の機会です。基礎学力の定着を図るためにも、夏期講習はマストといえます」
学齢に合わせたカリキュラムで「学ぶ楽しさ」を体験できる
日能研の夏期講習は学年ごとに狙いやプログラムが異なり、成長に応じて適切な学習を受けられるそうです。
邨田先生「4年生までは2部制で、前半・後半のどちらかに参加する形式です。どちらも同じプログラムなので両方参加する必要はなく、ご家庭で過ごす旅行やレジャーなどのスケジューリングもしやすいでしょう。一方、5年生以上だとお盆期間や休日以外は毎日授業があるので、夏休み全体を使ってしっかりと勉強していただいています」
日能研の場合、2年生から夏期講習に参加でき、低学年の授業では学ぶ楽しさを重視しているといいます。
邨田先生「算数の場合、先取りで高度な知識レベルの授業をしたり、受験テクニックだけに走ったりするのではなく、学齢に合わせたプログラムを実施しています。重視しているのは、『深く考える面白さ』を伝えることです。入室された理由をみても、『夏期講習が面白かったから日能研で頑張りたい』と言ってくださるケースが多くみられます」
一方、荒賀先生によると、低学年の夏期講習では興味の幅を広げる工夫を取り入れるそうです。
「普段より時間のゆとりがあるぶん、さまざまな話ができます。すでに日能研に通ってくれているお子様の場合は復習なので、1回目より話の幅が広くなるのもメリットです。また、低学年の間は質問を受けてもすぐに答えを言わず、ゆっくり考えてもらう時間をつくることもあります。時間にゆとりのある時期に考える余地をつくることが狙いです」
夏期講習は国語力アップにおいても重要なタイミングといえるようです。
「国語は暗記教科のように覚えたことが点数に直結するわけではないので、成長に時間を要します。普段の学習を血肉にできないことは多々あり、得点に結実させていくためには演習量を確保することが大切です。学校のない時期に無理なくできる夏期講習は、演習量を確保するベストタイミングといえます」
夜は自宅で夕食&振り返り。昼+夜のお弁当2食時代より合格率アップ
邨田先生「低学年は午前中のみ。高学年は午後開始で13時ごろから遅くても19時ごろまでです。6年生はお弁当1食分持ってきていただくこともあります」
そもそも、夏期講習は子どもたちが普段より元気な状態でエネルギーを注げることも大きなメリットだそうです。
荒賀先生「普段の授業は学校のあとなのでやはり疲れていますが、夏期講習の間は元気すぎるくらい体力があり余っています。問題を解く馬力も変わるので、吸収量の差も歴然です」
昼と夜の2食分を持参してもらっていた時代もあるそうですが、当時よりも今のほうが高い効果を感じているといいます。
荒賀先生「お弁当2食分をご用意いただき、9時から21時ごろまで授業をしていた時代もありましたが、お弁当1食だけにしてからのほうが圧倒的に集中しています。お弁当2食の時代は疲れてしまっていたうえ、自宅に帰ってから自分でする時間がとれないので、効果が上がりませんでした」
お弁当2食をやめたことで、合格率にも変化がみられたといいます。
荒賀先生「塾にいる時間を減らすために、より効果が上がると判断したものを優先して勉強してもらうことにしたのです。すると、お弁当2食分を持参していたころよりも合格率が明らかに上がったことに驚きました」
普段の授業でも夏期講習でも、大切なのはその日の授業をもう一度考え直してみることだそうです。
「塾で座っていたら力がつくわけではありません。むしろ、夜まで授業をするとやり直しの時間がとれず、やりっぱなしになってしまいます。元気な状態で集中して授業を受けて、家に帰ってから仕切り直して解き直すのがもっとも効率的です。近年の夏期講習では、自宅でリフレッシュしてから自分でもう一度考え直してみてもらうことを重視しています」
PDCAサイクルを早く濃密に回せるため著しい成長が期待できる
大人のビジネスシーンと同様に中学受験でもPDCAサイクルを早く回すことが大切だと、邨田先生が語ります。
PDCAサイクルとは、Plan(啓作)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の4ステップを繰り返すことで、継続的に業務を改善する手法です。一般的に、PDCAサイクルを回すことで業務や品質の向上を図り、目標達成率を高められるといわれています。
邨田先生「夏期講習は毎日あるので、その日感じた反省を次の日に活かせます。通常時なら同じ科目の授業は1週間後になることもありますが、翌日に改善のチャンスがあるのは魅力的です。普段からきちんと計画立てて宿題も丁寧にできる子ほど、夏期講習で得られる効果やメリットが濃密になるため、著しい成長が期待できます」
夏期講習で高い効果を狙うために、苦手の克服を目指す保護者の方も少なくないようですが、受講に向けて身構える必要はないといいます。
荒賀先生「夏期講習の時点で苦手の克服まで考えなくても構いません。ただし、何が得意か、何が苦手かは把握しておいてください。6年生は1学期の間にすべて網羅するのでチェックできるはずです」
得意・苦手を把握できていると、効率的かつ効果的に授業を受けられるそうです。
荒賀先生「事前にカリキュラムをお渡しするので、その日の単元を確認しておきましょう。『苦手だから今日は気合を入れておかないと』、『今日は好きな単元だから楽しく受けられたらいいや』など、授業にメリハリをつけられます。単元のチェックは6年生だけでなく5年生でもしておくとよいでしょう」
日能研の夏期講習では、お子様たちが元気いっぱいで勉強に励んでいます。学ぶ楽しさを味わい、きちんとリフレッシュしながら能動的な学習を受けられる環境です。中学受験の夏期講習は、夏を犠牲にするものでも、惰性で受けるものでもありません。成長の喜びを味わえる夏期講習を、ぜひ体感してみてください。
聞き手・文:古賀令奈