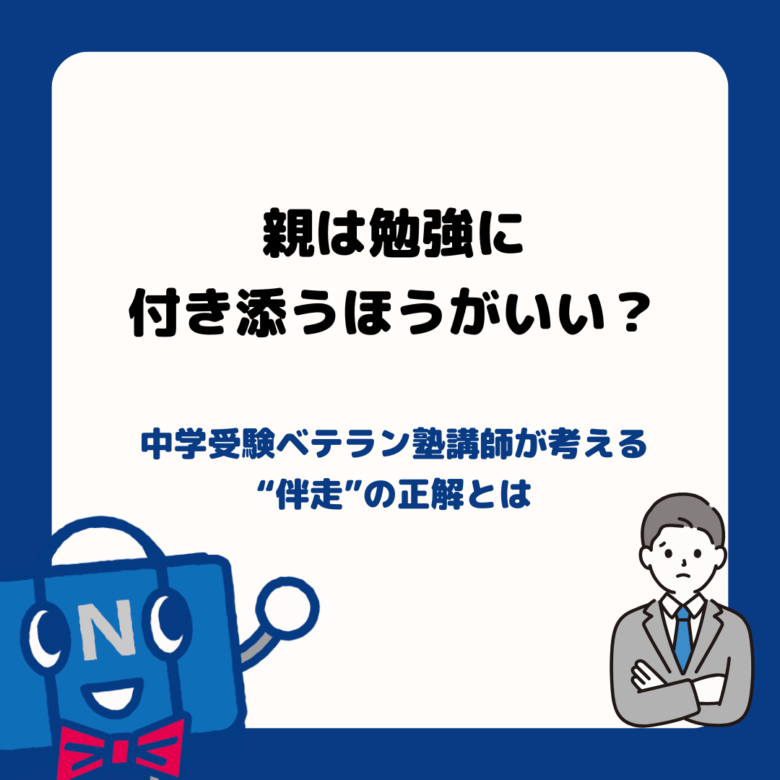
中学受験に励む娘をもつTさんからお悩みが寄せられました。「中学受験は家庭での伴走が大事と聞きますが、親は勉強に付き添ったほうがよいのでしょうか?」とお悩みの様子です。そこで、日能研のベテラン講師である荒賀先生と邨田先生のご意見をうかがいました。
勉強そのものを教えるより、見守りが重要
「自宅での学習サポートで合否が変わるかもしれないと思うと、親としてプレッシャーを感じます。家庭でも丁寧に教えてあげたいけど、自分にはそこまで教えてあげる力がなくて……」と不安げに語るTさん。
国語担当の荒賀先生が、Tさんに寄り添うように答えます。「親御さんの付き合い方としては、勉強そのものを教えるよりもきちんと見守ってあげることが大切です。まずは、お子様が集中できる環境をつくってあげてください」
とくに低学年の場合、集中できる環境は子ども部屋などではなく、親御さんの目が届くリビングやキッチンなどだといいます。
荒賀先生「お母様が料理や家事をされているところで勉強させるご家庭が多いと思いますが、テレビやおもちゃ、音楽などお子様の周りに集中力を欠くようなものはすべて排除して、目の前の課題に集中できる環境をつくってあげましょう。最初は5分、10分など短時間から始めて、15分、20分とのばしていくよう意識してみてください」
お子様の関心を誘う音楽などはNGですが、料理や家事などの生活音は推奨されるそうです。
荒賀先生「包丁で刻む音など、多少の雑音があるくらいがいいと思います。カフェで勉強をしたら集中しやすいという方が多いように、子どもも生活音のなかで勉強するのはおすすめです」
低学年のうちは丁寧に、成長に応じて少しずつ手を離していく
荒賀先生は、低学年から高学年にかけて、成長段階に応じて手を離していくことが大切だといいます。
「お子様が解かれた宿題は、正しい勉強を身につけるまでは一緒に答え合わせをしてあげるとよいでしょう。低学年のうちは、悪気はなくても間違えているものにマルをしたり、消しゴムで消して答えを書き直してマルにしたりすることがあります。『間違えたものはもう一度解き直すのが当たり前』と思えるようになるまで続けてあげるのが理想的です」
勉強の中身を教えるのではなく、勉強の正しいやり方が身につくようになるまで一緒に見てあげることが大切だそうです。
荒賀先生「保護者の方には、100か0で考える方が少なくありません。みっちり指導するか、一切手を出さなくなるか。極端に考えず、少しずつ本人に任せていくことが大切です。毎回のチェックを2回に1回にしたり、自分でできそうな問題は解かせてみたりと、お子様が自分でできる幅を広げていけるように徐々に手を離していきましょう」
算数担当の邨田先生も口をそろえます。
「自転車の補助輪をだんだん外していくようなイメージではないでしょうか。徐々に手を引きつつも、やはり親御さんにご協力いただきたい部分はあります。お子様の成長度合いによりますが、子どもだけで中学受験の細かなスケジューリングをこなしていくのはやはり難しいと思います」
スケジューリングは一緒に考えて、時間と成果物の管理は協力を
高学年の伴走で大切なことは、手を引くポイントを間違えないことだといえるでしょう。6年生でも親が積極的にサポートしたいのが、「時間」と「成果物」の管理です。高学年でも時間や成果物の管理は難しいケースが多く、保護者会などでもご家庭での協力を仰ぐそうです。
邨田先生「我々は塾での学習サポートはできても、お家に帰ってからの時間管理までは物理的に厳しいため、親御さんにご協力いただけると助かります。1週間の家庭学習の成果物のチェックなども同様で、ぜひサポートいただきたい要素です」
荒賀先生「スケジュールの管理は親御さんがぜひ一緒に計画を立ててあげてください。例えば、1週間のスケジュールを考えて、『宿題はいつしよう』『何時からしよう』といったように、お子様が遂行しやすいスケジューリングに仕向けましょう。一緒に考えて、お子様に納得感をもたせることがポイントです」
効率的な解き方が悪影響を招くことも、勉強を教えるときは塾の方針にあわせて
親御さんが指導する場合、本来はまだ教わる段階ではない効率的な解き方を教えるケースがみられるそうです。しかし、大人にとっては簡単にできる方法でも、子どもにとっては望ましい方法ではないといいます。
邨田先生「塾では学齢に応じた知識をもって解けるように、学年ごとに適した解き方を指導しています。大人には簡単に感じても、低学年の子にはとても高度な概念であるケースも少なくありません。その分析を行ったうえで指導するのはとても難しいことですが、逆に言うと我々の存在意義はそこにあります」
もっとも多いのが、方程式を使って解く方法を教えるケースだそうです。
邨田先生「方程式を使って解くほうが早いのは正論ですが、なぜそれを中学校で教えているのか。そこにはちゃんと理由があります。ごく一部のお子様は難しい解き方にも興味を示して吸収することがありますが、ほとんどのお子様はレールの敷き方を間違えると脱線しやすくなります。遠回りに感じても順を追って学んでいくことが大切です」
では、家庭学習で子どもに指導をするとき、どうやって教えればいいのでしょうか。
邨田先生「日能研は成長の度合いに合わせたやり方を重視しているので、塾のノートや解説をしっかり見ていただき、同じやり方でお子様に寄り添っていただけるといいと思います。解説動画もあるので、そちらもぜひご覧ください」
子どもに寄り添うということは、手や口を過度に出すことではなく、状況に応じて必要なサポートを見極めることだといえるでしょう。お子様のことを思えば思うほど、何をどうすべきかわからなくなることもあるでしょう。日能研では、家庭学習の指導相談にも対応しています。ご家庭をよりよい環境にしていくためにも、ぜひご相談ください。
聞き手・文:古賀令奈
