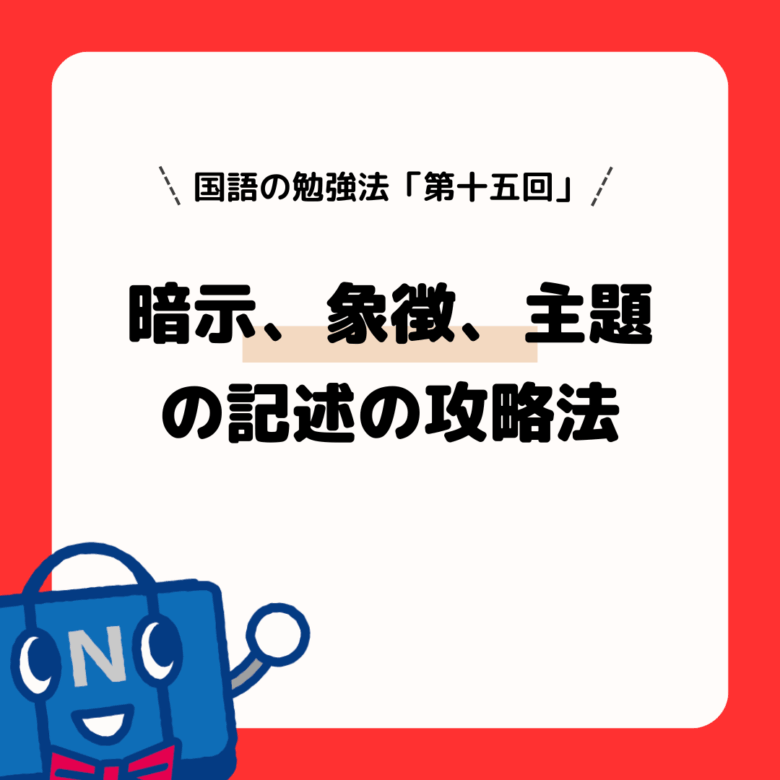
今回は、物語文における、暗示・象徴の記述の考え方と、主題をからめた記述問題の考え方をお話しします。
「暗示」とは、これから起こることを前もってそれとなく示すことで、「象徴」とは、目に見えない抽象的なことがらを表現するために、目に見える具体的なものを用いて表現することです。この「暗示」や「象徴」が使われている物語文が入試問題で取り上げられたときは、「暗示」している内容を説明させる問題や、どういったことを象徴しているのかを説明させる問題がよく出題されます。
暗示されていることや、象徴していることを答えるときは、その文章の主題と関連づけて考えることが大切になります。言いかえれば、主題に関連した内容が「暗示」されることが多く、また主題を表現するために「象徴」が用いられるということです。ですから、初めに「主題」を読み取るにはどのようなことに気をつければいいのかについて、説明したいと思います。
主題とは、その文章を通して作者が伝えたいことを言います。主題を読み取るときに注目してほしいことは2つあります。1つ目は、「変化」に着目することです。物語文では、ある出来事をきっかけとして、主人公の心情や考え方が変化していく様子が表現されるものが大半です。物語の始めの部分での主人公の心情や考え方が、後半でどのように変化したのかをつかみます。その変化を通して主人公の成長や価値観の変化などを読み取りましょう。そしてその変化から主題を考えるようにします。2つ目は、主人公の考え方や価値観が読み取れる発言や行動に着目することです。作者が読者に伝えたいことは、主人公の発言や行動に投影されます。作者が主人公、または主人公に影響を与えている人物に、どのようなことを語らせているかに注目してみてください。
次に「象徴」について見ていきます。「象徴」の説明問題は、比喩の説明問題の解き方と似ています。抽象的な事柄を具体的なもので置き換えて表現しているのが「象徴」ですので、その「具体的」なものの持つイメージを頭の中で思い浮かべることが大切です。そしてその具体的なものの持つイメージと文章の主題とが、どのように関連しているのかを考えてみると、「象徴」の問題を解くことができます。たとえば、孤児院で暮らす少年が、親戚の家で暮らしたいという希望を持って親戚の家を訪ね、いい返事をもらうことができたという内容の話で説明してみましょう。その夜、寝ているときに「蛍」が飛んでいるシーンが描かれていたとします。この「蛍」が象徴している内容を考えてみましょう。蛍は「光る」という特徴を持った虫ですね。この少年は親戚の家で暮らしたいという希望を持っているわけですから、少年の希望は蛍の光に置きかえて表現されていると言えるでしょう。
最後に「暗示」について説明します。この先物語がどういう方向へ進んでいくのかを暗示するために、情景描写を用いたり、「象徴」とからめて表現したりします。まず、情景から説明します。描写されている風景や周りの様子がもつイメージをしっかりつかむようにしてください。たとえば、さわやかに晴れた青空が表現されていれば、主人公にとって良いことが起こることの暗示だと理解できます。また、親子関係を描いた物語で、夕日が描かれていれば、夕日のオレンジから温かいイメージを手がかりにして、親子関係の好転や、絆が深まるような内容が暗示されていることを読み取ります。また「象徴」とからめて考える問題については、先ほど例にあげた、孤児院で暮らす少年の話で説明してみたいと思います。寝ているときに「蛍」が飛んでいるのは、「親戚の家で暮らすことができるという希望の光」を表しているわけですが、この「蛍」いつの間にかいなくなっていたとしましょう。そうすると、「希望の光」が消えたわけですから、これは、この先何らかの事情で親戚の家で暮らせなくなるということを暗示した表現だと理解できるわけです。このように、「象徴」の内容を利用することで、「暗示」の問題が解けることもよくあります。
暗示、象徴、主題に関する設問は、文章全体を理解していないと解くのが難しい問題です。今回の説明を参考にして、このような難問にもうまく解答が導き出せるようになってくださいね。
