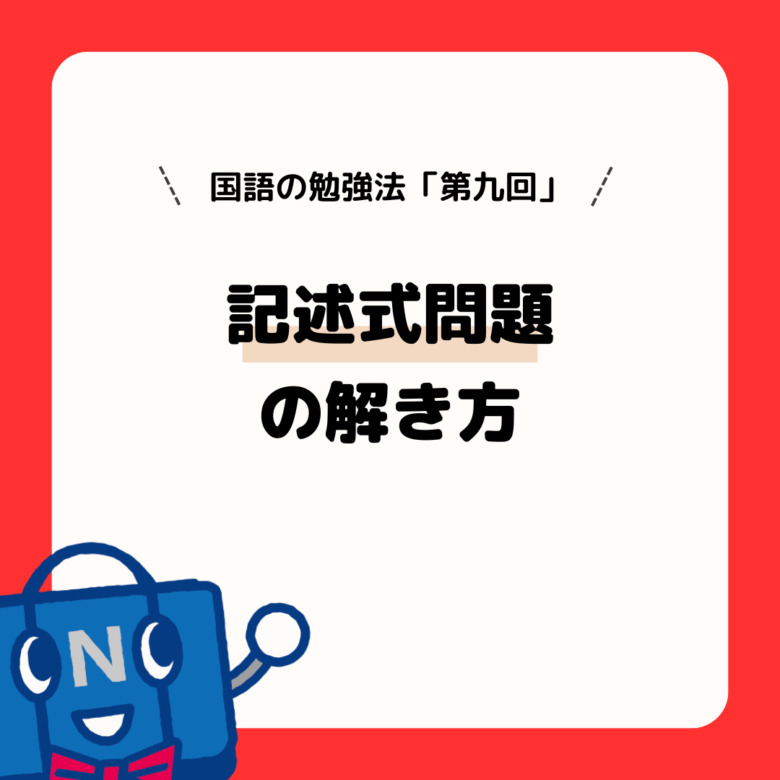
今回は記述式問題の解き方についてお話します。記述式問題には具体化の記述や理由の記述、心情の記述など、いくつかのパターンがあります。そのパターンそれぞれに解法があるのですが、それは次回以降詳しく説明していきます。今回は記述式問題全般の考え方について見ていきたいと思います。
記述式問題を解くときに初めに行ってほしいのは、設問の分析です。何が問われているのかを正確に理解していなければ、ピントのぼやけた解答を書いてしまう可能性があります。出題者の出題意図を考え、出題者の求める解答を書く。これが記述式問題で一番大切なことです。記述式問題の典型的な設問パターンには、具体化の記述、相違点の記述、比喩の記述、理由の記述、心情の記述、暗示・象徴の記述、要約型の記述などがあります。それぞれの解法パターンに合わせて、解答を考えていくことになります(初めにも述べましたが、パターン別の解法については次回以降説明します)。
設問の分析ができたら、解答の根拠となる部分をさがし、説明するべき点を整理します。このとき、採点の基準となる要素がいくつあるかを意識して、説明するべき点をまとめておくことが重要です。説明するべき要素が何ポイントあるかを考えないで答案を作成すると、何を伝えたいのかがよくわからない文章になることが多く、注意が必要です。
説明するべきポイントがつかめたら、解答の要素をどの順序で説明すればわかりやすい答案になるか、解答の要素をつなぐ論理は何かを考えて、解答を頭の中で作成します。そして、頭の中で解答がまとまった段階で、一度下書きをします。次に、下書きを見て推敲します。字数制限のある問題では、制限字数に収まっているか、極端に字数が足りないことはないかをチェックしてください。制限字数をかなりオーバーしている場合は、説明しなくてもいいことまで書いてしまっています。また、字数が明らかに不足している場合は、説明するべき要素が漏れています。これらの場合は、もう一度本文を読み直し、答案を作成し直しましょう。推敲する際は、主語と述語が対応した文章になっているか、修飾関係がはっきりわかる文章になっているか、誤字脱字がないかを確認してください。また、出題された文章を読んでいない人が答案を見た時に、具体的な内容が伝わるレベルの答案になっているかという視点で見直すことも重要です。出題された文章を読んでいない人が理解できない答案は、解答としては説明不足になっています。答案の内容に疑問が残る部分に注目して、再度答案を書き直すようにしてください。
ただし実際の入試では、下書きをして推敲する時間が取れないこともありますので、そのときは頭の中で推敲まで終わらせてしまい、一気に解答用紙に答えを書くようにします。
続いて、記述式問題を解く力を身につけるための、間違い直しのやり方を説明します。まず模範解答をよく読み、説明するべき要素がいくつあるかを確認します。そして、なぜその要素が解答には必要なのかを考えてください。次に、解答の要素となる部分が、本文中のどこに書かれているかを探しましょう。傍線部分から解答の要素となる部分を見つけるための論理を考えるようにします。はじめは解答の根拠となる部分を見つけるための論理がよくわからないこともあるかと思いますが、自分なりの理屈でいいので、考えるようにしてください。何度も練習していくうちに、論理的に考える癖が身についていきますので、次第に根拠となる場所を見つけられるようになっていきます。
さて、書くべき要素がおさえられたら、模範解答を見ずに、自分で解答を書き直してみるようにしましょう。相手に伝わるわかりやすい日本語が書けるようになるためには、この書き直すという作業が重要です。書いた量に比例して、日本語を書く力は上達していきます。
今回は記述式問題の全般的な考え方を説明しました。次回からは設問パターン別に、記述式問題の解法をお話ししていきます。
