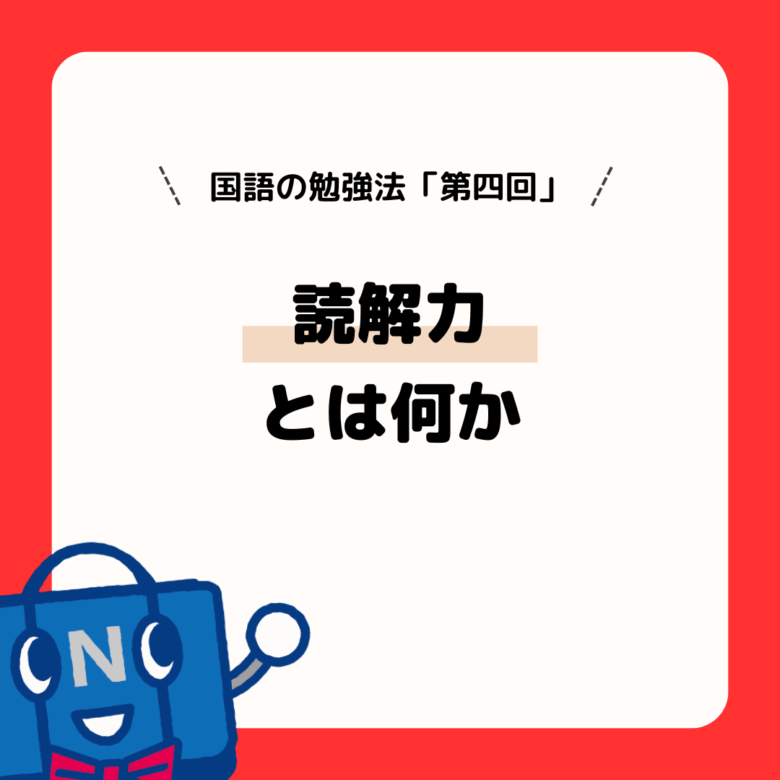
「国語のテストで点数を取るには、読解力を身につけることが大切だ」という話をよく耳にしますが、読解力とはどういう力のことをいうのでしょうか。読解力が大切だとは理解できるものの、どういう力のことなのかをはっきり意識しないまま使われている言葉だと言えます。そこで今回は、中学入試を突破するために身につけるべき読解力についてお話ししたいと思います。
読解力とは、文字通り「読んで解る力」のことです。つまり、文章を読んで、文章の内容を正しく理解するのが読解力です。では、「文章の内容を読んで、文章の内容を正しく理解する」とは、どういうことなのでしょうか。それが分かれば、読解力を身につけるために、どのような練習を積めばよいのかが見えてきます。論説文と物語文とでは、「文章の内容を読んで、文章の内容を正しく理解する」ことに、多少の違いがありますので、別々に説明していきたいと思います。
まず論説文では、何について論じた文章なのかをつかみ取り、筆者の主張をその主張の論拠とともに理解することが求められます。筆者の主張は、文章中で形をかえて繰り返されていきます。その言いかえられた表現を正しく追いかけていく力が必要となります。これを「類比」と言います。抽象的な主張を、わかりやすく具体例をあげて説明している部分も類比ですし、イメージを直感的にとらえさせるために用いられる比喩も類比です。また、筆者と同じ考え方をしている人の文章を引用している部分があれば、これも類比と言えます。
また、私たちがものごとを認識するとき、対立する二つの事柄の中で理解していることがよくあります。たとえば、「明るい」を理解しようと思えば、反対の「暗い」という状態が分かって、初めて「明るい」のか、そうでないのかが理解できるはずです。論説文の筆者は、自分の主張を述べる際、その対立する事項をあげて説明することがよくあります。比較することによって、説明したい事柄が際立って見えるようになるからです。このように、対立する内容を用いて説明することを「対比」と言います。
そして、筆者が何らかのことを主張したとき、そこには論証責任が生じます。なぜそのようなことが言えるのか、その理由を説明しなければ、読者を納得させることができないからです。つまり、論説文では「因果関係」を理解し、読み進めていく必要があるわけです。
ですから、論説文では、「類比」、「対比」、「因果関係」を読み解く力を身につけ、文章の論理展開を正しく理解して、筆者の主張を正確につかみ取ることができるようにならなければなりません。これが論説文における読解力です。
それでは続いて、物語文における読解力について説明します。物語文の読解力の基本となるのは、場面を正確にとらえ、それぞれの場面における登場人物の心情を読み取ることです。また、その物語を通して作者が何を伝えたいのかという主題を理解する力も求められます。場面は、「いつ(時間)」、「どこで(場所)」、「だれが(登場人物)」、「どうした(出来事)」の四つの要素で構成されます。まずはこの四つの要素を意識して文章を読み、物語のあらすじを正確に追えるようになることが大切です。
次に、心情を理解するには、その心情が生じたきっかけとなる出来事が何かを、読み取ることが必要となります。また、登場人物の心情は、心情表現を使って直接書かれていることはほとんどありません。登場人物のとった行動や動作によって示されたり、比喩を使って表されたりします。また、会話文から心情を読み取ったり、情景描写から理解したりすることも求められます。この「出来事」→「心情」→「行動」という一連の流れが繰り返され、物語は展開していきます。ですから、この流れを正しく追って文章を読み進めることが、物語文の読解では大切になります。さらに、その物語のテーマとなる主題が何かまで考えて読むことができれば、物語の読解は完璧です。
読解力とはどのような力のことなのか、理解いただけたでしょうか。しかし、どのような力なのかが分かっただけでは、まだ不十分です。なぜなら、読解力を身につける方法まで知って、初めて役に立つものとなるからです。次回は、読解力を身につけるための効果的な学習方法についてお話ししますので、楽しみにしてください。
