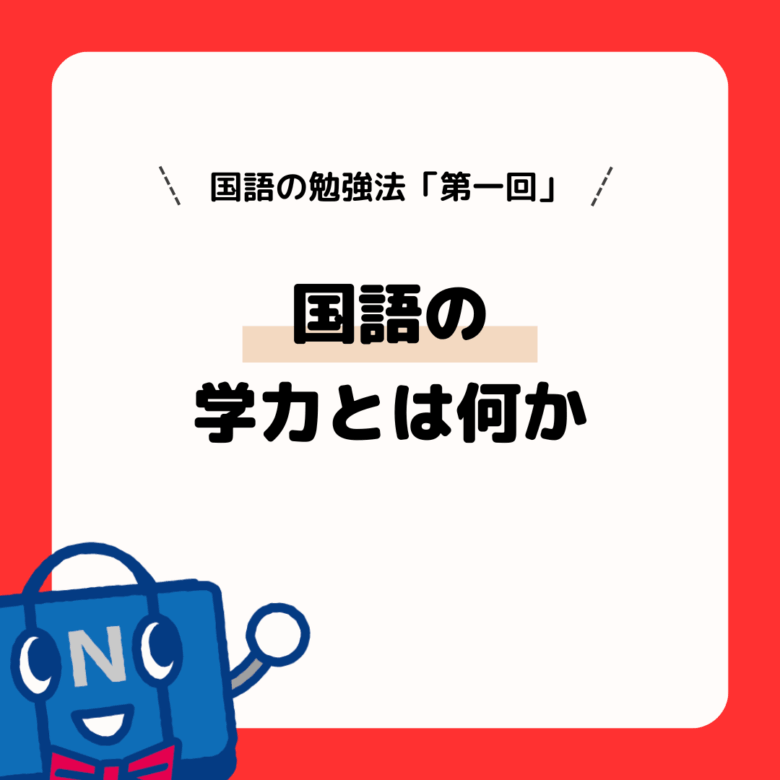
国語ってどういうやり方で勉強すればいいのかよくわからない。こんな相談をこれまでに何度も受けてきました。読者の方にも、同じ悩みを持つ方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方のために、国語の効果的な学習方法について、わかりやすく説明していきたいと思います。
今回は、そもそも「国語の学力」とは何なのかについて、お話しします。身につけるべき「国語の学力」が何かを理解することで、どんなことを意識して学習すれば良いかがわかります。
中学入試で求められる「国語の学力」は、大きく三つに分けられます。一つは「知識力・語彙力」。もう一つは、文章に書いてある内容を正確に理解する「読解力」。そして三つめは、理解した内容を、相手に正しく伝えるための「記述力」です。
とりわけ近年の中学入試では、記述式で解答を求める出題が多く見られるため、しっかりとした「記述力」が身についているかどうかが、合否を分けると言っても過言ではありません。ですから、保護者の方の学習相談も、「うちの子はまったく記述が書けない」という内容が一番多いように思います。
では、その「記述力」は、どういう練習をすれば身につくのでしょうか。記述式の問題で得点をとるには、当たり前のことですが、文章の内容を正しく理解できていなくてはなりません。いくら正しい日本語表現で答案が書けていても、書いている内容が間違っていれば、当然正解にはなりません。
さらに、設問で何が問われているのかという、作問者の出題意図をくみ取る力も必要です。例えば、問題文の同じところで設問が作られていたとしても、「どういうことですか、説明しなさい」と、「どういうことですか、わかりやすく説明しなさい」と、「どういうことを言おうとしていますか、説明しなさい」では、全て解答が異なります。なぜこのようなことが起こるのかというと、作問者が受験生に求めている解答によって、問い方を変えているからです。
しかし、答案に書くべき内容が分かったとしても、まだ正解できるとは限りません。自分の理解した内容を相手に過不足なく伝えるための、日本語作成能力が必要となるからです。
つまり、記述式の問題で得点をとるための「記述力」を身につけるには、文章を正しく理解する力(=「読解力」)と、設問の意図を正しく理解する力と、正しく日本語を書く力という、三つの力を習得しなければなりません。
それでは、「読解力」を身につけるには、どうすればいいのでしょうか。それは文章を論理的に読む練習を積むことです。しかし、語彙力がなければ、文章を論理的に読むことはできません。
さあ、これで中学入試において求められる国語の学力がどういうものか、わかってきましたね。まず、語彙力がなければ文章は正しく読めません。次に、文章を論理的に読まなければいけません。そして、設問の意図を正しく理解し、適切な日本語表現ができなければ、得点につながりません。
このコラムでは、知識力・語彙力を身につけるための効果的な学習法や、論理的に文章を読めるようになるための練習方法を具体的に説明していきます。さらに、作問者の出題意図をふまえた設問別の攻略法、適切な日本語表現ができるようになるための学習方法も紹介していきますので、次回以降も楽しみにしてください。
