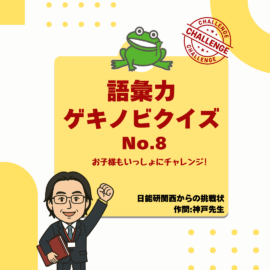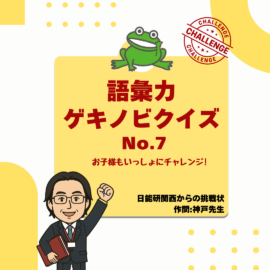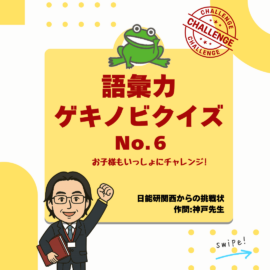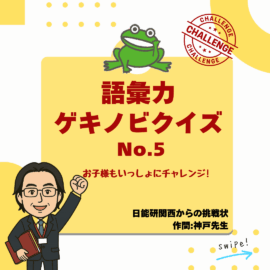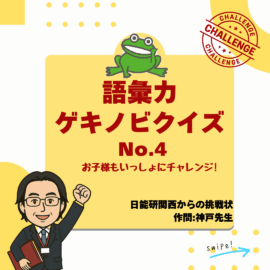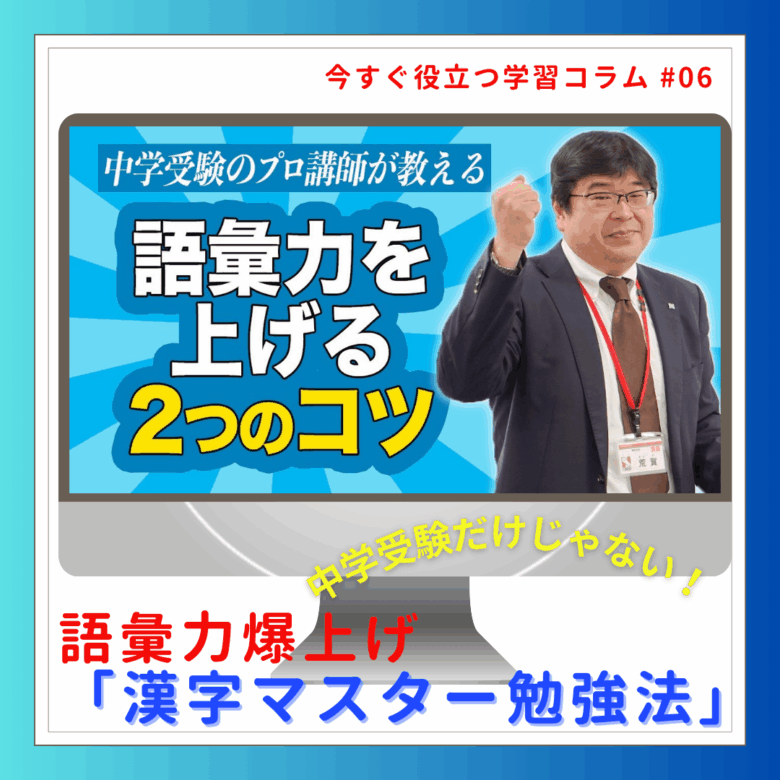
「文章がなかなか理解できない」「語彙力が足りない」と感じることはありませんか?実は、語彙を効率的に増やすための近道があります。それは、漢字の意味を理解することです。日本語の言葉の多くを占める「漢語」の仕組みを紐解き、漢字一文字一文字の意味をしっかりと捉え、さらに二字熟語の組み立て方を学ぶことで、知らない言葉でも意味を推測できるようになり、読解力は飛躍的に向上します。この方法で、言葉の世界は劇的に広がるでしょう。
語彙力アップは読解力のカギ!「知らない言葉」を減らすには?
文章を読み解く力は、すべての教科の土台となる非常に重要な能力です。そして、その読解力を支えるのが、まさに「語彙力」に他なりません。知らない言葉が多ければ、文章全体の意味を正確に把握することは困難です。では、どのようにすれば効率的に、そして確実に語彙力を増やせるのでしょうか?
日本語の語彙を増やす上で、最短ルートといえるその方法は、「漢字」をマスターすることです。
日本語に最も多い「漢語」を理解する
日本語は、大きく分けて三種類の言葉から成り立っています。
・漢語(かんご):中国から伝来した言葉で、漢字を元に作られたもの。「学校」「勉強」など。
・和語(わご):古くから日本にあった、日本の文化や生活に根差した言葉。「山」「歩く」など。
・外来語(がいらいご):他の言語から借用された言葉で、主にカタカナで表記される。「テレビ」「パソコン」など。
この中で、圧倒的に数が多いのが「漢語」です。そのため、漢字の持つ意味をしっかりと覚えることは、語彙を一気に増やすための決定的な鍵となります。
漢字一文字の持つ「意味」を探求する
漢字学習と聞くと、「形を覚える」「読み方を覚える」というイメージが強いかもしれません。しかし、語彙力向上のためには、さらに「漢字一文字が持つ意味」を確認し、覚えることが大切です。
例えば、「服」という漢字。多くの方は「洋服」や「衣服」という意味を思い浮かべるでしょう。しかし、もう少し詳しく調べてみると、「人に従う」という意味も持っていることがわかります。この「従う」という意味を知ると、「服従(ふくじゅう)」という熟語の「服」が、単に身にまとう「服」という意味ではないことが理解できるようになります。
このように、漢字一文字の持つ多様な意味を知ることで、これまで知らなかった熟語に出会ったときも、その意味を推測する手がかりとなり、言葉の世界がぐんと広がっていくのです。
熟語の「組み立て」を理解すれば、未知の言葉も怖くない!
ほとんどの漢字は、文章の中で「二字熟語」の形で登場することが多いです。この熟語の意味を推測する上で非常に役立つのが、「熟語の組み立て」を意識することです。熟語には、成り立ちにいくつかのパターンがあります。このパターンを知っておくと、初めて出会う熟語でも「おそらくこういう意味だろう」と予測する力が養われます。
主な熟語の組み立て方は以下の5つです。
同じ意味の漢字を重ねているもの
・例:「思考(しこう)」…「思う」と「考える」という似た意味の漢字が重なっています。
・例:「道路(どうろ)」…「道」と「路」という、どちらも「みち」を意味する漢字が重なっています。
反対の意味の漢字を重ねているもの
・例:「明暗(めいあん)」…「明るい」と「暗い」という反対の意味の漢字が組み合わされています。
・例:「遠近(えんきん)」…「遠い」と「近い」という反対の意味の漢字が組み合わされています。
上の漢字が下の漢字を修飾しているもの
・例:「青空(あおぞら)」…「青い」という上の漢字が「空」という下の漢字を詳しく説明しています(青い空)。
・例:「動画(どうが)」…「動く」という漢字が「画(え)」を修飾しています(動く画)。
下の漢字が上の漢字の目的語になっているもの(下から上に読んで意味が通じるもの)
この場合、下の漢字には「を」や「に」などの助詞が隠れていると考えると理解しやすくなります。
・例:「登山(とざん)」…「山に登る」と下から上に読みます。
・例:「読書(どくしょ)」…「書物(しょもつ)を読む」と下から上に読みます。
主語と述語の関係になっているもの
・例:「私立(しりつ)」…「私(個人)が設立した」という関係です。
・例:「市営(しえい)」…「市が営んでいる」という意味合いになります。
これは、「何がどうする」という関係性で熟語を捉えるパターンです。
これらの組み立て方を知識として持っておくことで、初めて見る熟語でも「これはきっと〇〇のパターンだから、こういう意味だろう」と推測する力が格段に向上します。
まとめ
漢字を「書ける」「読める」だけでなく、「意味を深く理解する」ことに焦点を当てる学習法は、単に語彙が増える以上の効果をもたらします。漢字一文字の持つ複数の意味を知り、さらに熟語の構造を意識することで、文章の中で出会う知らない言葉の意味を自力で推測できるようになり、結果として文章読解力は飛躍的に向上するのです。
今日からぜひ、漢字一つ一つの意味に、より関心を持って接してみてください。あなたの言葉の世界が、これまで想像もしなかったほど豊かになるはずです!
このコラムの内容は動画でも解説しています。
もっと知りたい方はこちらの動画をごらんください。