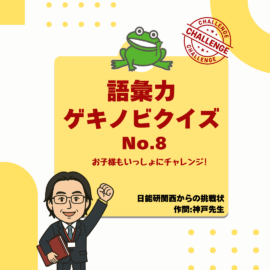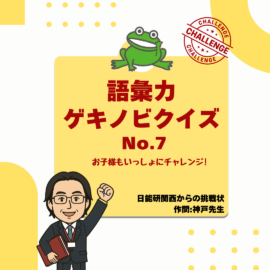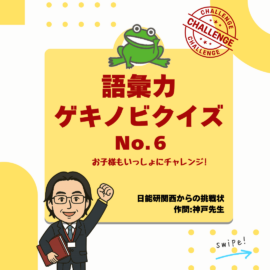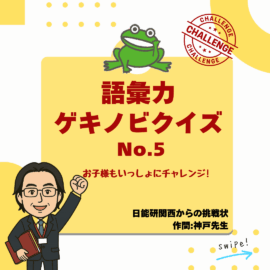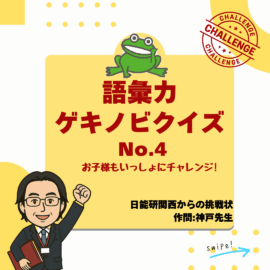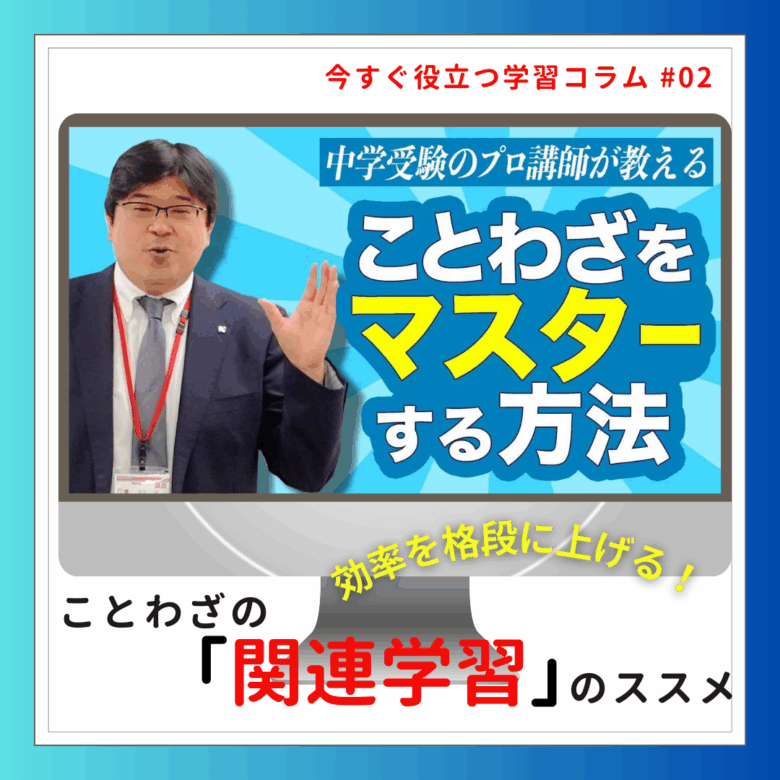
「中学受験」の国語対策として、ことわざ学習は非常に重要です。ただ単にことわざを暗記するだけでは不十分で、その意味や使い方、さらには関連する知識と結びつけて学ぶことが、効率的な国語力向上への鍵となります。今回は、一つのことわざから知識を何倍にも広げ、楽しく確実に定着させるための具体的な学習法をご紹介します。
「ことわざ」を学習して得点力をアップ
国語の勉強、特に中学受験を目指すお子さんにとって、ことわざの習得は避けて通れないテーマです。ことわざは、私たちの祖先が経験から得た知恵や教訓が凝縮された言葉で、知識問題として直接出題されることも多いため、早期からの確実な学習が求められます。
しかし、「ことわざ」と聞くと、たくさんあって覚えるのが大変だと感じる方もいるかもしれません。ご安心ください。ただ闇雲に暗記するのではなく、効率的で楽しい学習法を取り入れることで、子どもたちは自然とことわざの知識を広げ、国語力を高めることができるのです。
ことわざ学習の第一歩:基礎を固める
ことわざ学習を始める上で、最も基本的ながら重要なステップは、「ことわざそのもの」と「その意味、使い方」をしっかりと覚えることです。例えば、「蛙の子は蛙」(かえるのこはかえる)ということわざを知らなければ、問題に答えることはできません。まず「こんなことわざがあるんだな」と認識することから始まります。
次に、「蛙の子は蛙」が「親と子は似るものである」という意味だと理解し、具体的に「どのような場面で使うのか」というニュアンスまで把握することが大切です。この意味や使い方を覚える際には、ただ活字を追うだけでなく、学習漫画などの視覚教材を大いに活用することをおすすめします。漫画で具体的なシチュエーションとともにことわざが描かれていると、記憶に残りやすく、どのように使うべきかのイメージも湧きやすくなります。「この状況でこのことわざを使うんだな」と、記憶が定着しやすくなるでしょう。
知識を何倍にも!「つながり」で覚える応用学習法
基礎が固まったら、ここからがことわざ学習の真髄です。一つ覚えたことわざを『核』として、そこからどんどん知識を広げていく「応用学習法」を取り入れましょう。
1. 「同じ意味」のことわざを一緒に覚える
「蛙の子は蛙」という親子の似た性質を表すことわざを覚えたら、次に「瓜の蔓に茄子はならぬ」(うりのつるになすびはならぬ)という、これもまた「親と子は似るものである」という意味のことわざを一緒に学びましょう。このように同じ意味のものをセットで覚えることで、知識が2倍、3倍と効率的に増えていきます。
2. 「反対の意味」のことわざもセットで覚える
さらに知識を増やすには、覚えたことわざと「反対の意味」を持つことわざも一緒に学ぶのが効果的です。例えば、「親と子は似るもの」という意味の「蛙の子は蛙」に対して、「平凡な親から優れた子が生まれる」という意味の「鳶が鷹を生む」(とびがたかをうむ)を合わせて覚えるのです。これにより、一つのことわざから関連する知識がさらに広がり、より深い理解に繋がります。
3. 「関連する言葉」からさらに広げる
覚えたことわざに出てくる「キーワード」をきっかけに、さらに別のことわざや慣用句を探してみましょう。例えば、「蛙」が登場する「蛙の子は蛙」を学んだら、「蛙」を使った別の言葉はないかな?と調べてみるのです。そうすると、「井の中の蛙大海を知らず」(いのなかのかわず たいかいをしらず)や「蛇に睨まれた蛙」(へびににらまれたかえる)といった、新しいことわざや表現が見つかるはずです。同様に「鳶が鷹を生む」から広げるなら「鷹」が登場する言葉を調べてみるといった具合です。 一つの核となる言葉から周辺知識をどんどんくっつけていくことで、まるで一本の木が枝葉を広げていくように、言葉のネットワークが構築されていくイメージです。
知識を定着させる秘訣:反復と楽しみながら学習する
せっかく覚えた知識も、一度きりでは忘れ去られてしまうものです。学習漫画などでことわざの意味や使い方、シチュエーションを理解したら、繰り返し何度も学習することが何よりも大切です。一度見ただけで覚えることは難しいですが、2回、3回と繰り返して目にするうちに、確かな自分の知識として定着していきます。基本的な知識が身につていると、学年が上がり授業などで関連する言葉に触れたときの吸収スピードが格段に上がります。
また、この学習プロセスを「楽しい」ものにすることも重要です。お子さんと一緒に「蛙」を使ったことわざを調べたり、「鷹」を使ったことわざを探したりする「調べ学習」を、ゲーム感覚で楽しんでみてはいかがでしょうか。親子で一緒に探求することで、学習へのモチベーションも高まり、より深い学びへと繋がるはずです。特に動物や植物が入ったことわざ・慣用句は入試で狙われやすい傾向にありますので、是非取り組んでみてください。
早い時期からこのような学習法でことわざに親しんでおくことは、小学校6年生になり、いよいよ中学受験の「読解」がメインになる時期に大きな力を発揮します。知識問題が解けることで基礎点をかせげるので、精神的な余裕も生まれるでしょう。
まとめ
ことわざ学習は、ただの暗記科目ではありません。一つのことわざから、同じ意味、反対の意味、そして関連する言葉へと知識の輪を広げていくことで、お子さんの語彙力は強化されていきます。
学習漫画を活用し、意味や使い方を楽しく学ぶ。 「同じ意味」「反対の意味」「関連する言葉」で知識を体系的に広げる。 そして、何よりも「繰り返しの学習」を習慣にする。
この3つのポイントを意識して、親子で楽しみながらことわざの世界を深く探求してみてください。中学受験だけでなく、その先の人生においても役立つ「生きた国語力」が、きっと身につくはずです。さあ、今日から「ことわざマスター」への第一歩を踏み出しましょう!
このコラムの内容は動画でも解説しています。
もっと知りたい方はこちらの動画をごらんください。