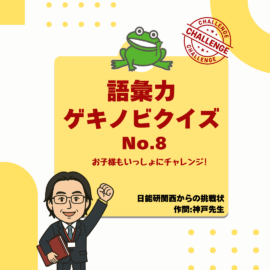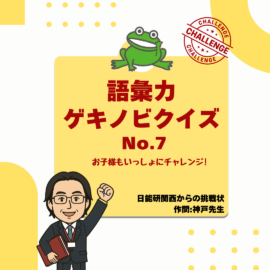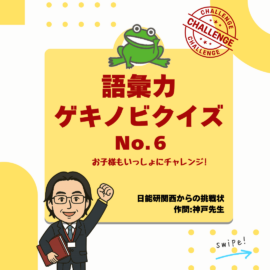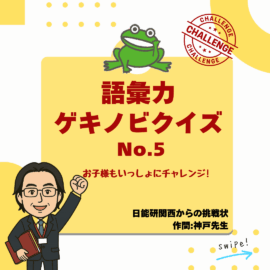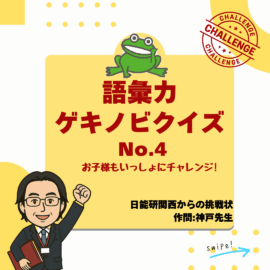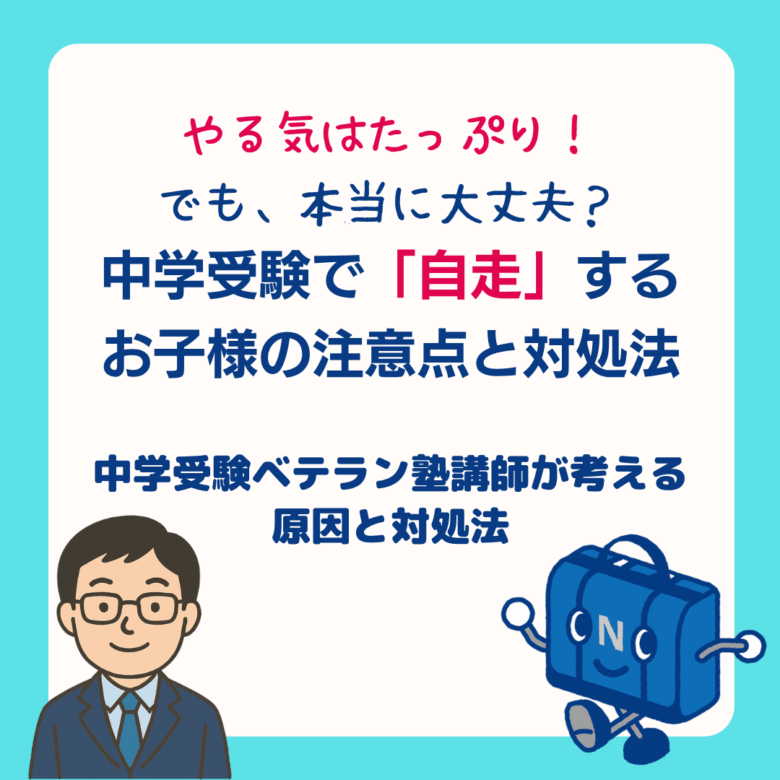
「娘はやる気満々で、スケジュール管理も勉強も自発的にしています。熱心なのはうれしいですが、本当にちゃんとできているか心配で……」とお悩みのTさん。中学受験で「自走」できる子は一見理想的に思えますが、意外なリスクも潜んでいるようです。Tさんのお悩みについて、日能研のベテラン講師である荒賀先生と邨田先生のご意見をうかがいました。
注意点1:「自分でスケジューリング」は実現不可能なプランの可能性あり
「毎日のスケジュールも勉強も、すべて娘が自己管理しています。休日は10時間勉強するなど頼もしいのですが、小学生の計画や判断に委ねた状態のままで本当に大丈夫なのか心配です」と語るTさん。国語担当の荒賀先生が答えます。
荒賀先生「やる気たっぷりな子は非常にタイトなスケジュールを組むことがあります。ぎっしり詰まったスケジュールだと実行するのが難しいため、お子様が自己管理するのは望ましくありません。スケジュールを立てるときは、時間に猶予を残しておき、自由に伸縮できるようにしていただきたいです」
最初はハードなスケジュールをある程度実行できたとしても、継続するのは難しいといいます。
荒賀先生「しんどい時期も体調を崩す時期もあります。学校が忙しくて勉強時間を確保できなかったり、疲れて体力的に厳しいときもあったりするでしょう。1年間全力では走り切れません」
無理のないスケジュールに誘導を
1年間無理なく勉強を続けるには、時期に合わせて調整することが大切だそうです。
荒賀先生「体調不良や学校行事などで勉強量の調整をするときは、何を優先すべきか、何を省くべきかを判断する必要があります。お子様が独自で判断するのは難しいので、我々に聞いていただきたいです」
算数担当の邨田先生によると、お子様が無謀なスケジュールを立てる場合、親御さんが付き添って無理のないように促すとよいそうです。
邨田先生「適正になるように止めてあげてください。やる気があるときのテンションで立てた計画は、やる気のないときには非常に厳しいものです。誰しも経験があることだと思いますので、親御さんの体験をもとに伝えてくださると、お子様の胸に響くでしょう」
そして、大切なのは子どもの意思で決めたように思わせることだといいます。
邨田先生「親御さんが指示していくとお子様は受け身になり、やる気が削がれてしまうかもしれません。お子様の意見を聞きながら親御さんも提案し、『一緒に考えたことだからきっちり守ろうね』という形にすると、自立心を損なうことなくサポートできます」
注意点2:「10時間頑張ったよ!」勉強時間の長さに価値をつけるとムラが出やすい
「意欲的な日は、『今日は10時間勉強する!』と目標を立てて頑張っています。長時間勉強した日は『すごいね』と褒めていますが、これは間違っているのでしょうか?」と気に病むTさん。
勉強時間の長さを重視しているご家庭は、意識の持ち方を変える必要があるそうです。
荒賀先生「勉強時間の長さに価値を見出すと、ムラができやすくなります。『今日は頑張ったけど明日はやらない』といったムラが生まれやすくなるので、勉強時間の長さを重視する考え方はおすすめしません」
長時間頑張った日は親心として褒めてあげたくなりますが、意識のムラを助長するような声かけは控えたほうがよいでしょう。
「やり切る」勉強スタイルに切り替えよう
勉強時間の長さに重点を置かないのであれば、一体何を重視すべきなのでしょうか。
荒賀先生「やるべきことをやり切ることが大切です。たとえば、『3時間勉強しよう』ではなく、『これをやろう』という気持ちで取り組んでください。逆を言えば、その目標を終えるまでは3時間経とうが4時間過ぎようがやり続けなければいけなくなります。すぐに終わればそのまま終わって構いません」
やり切る勉強法に変えることで、お子様の意識も変わっていくようです。
荒賀先生「早く終われば遊べるほうがよいでしょう。時間がかかればそれだけ遊べなくなります。お子様自身に『やるべきことが終わるまでやる』という意識が根付くと、勉強への向き合い方が変わるはずです」
小学生にして「自走」する意識は素晴らしいものの、スケジュール管理や勉強の取り組み方に改善の余地があるお子様は少なくないようです。お子様のやる気を尊重しながら、親子で一緒に無理のないスケジュールを立て、日々の目標をやり切る勉強法に切り替えることをおすすめします。
日能研では、保護者会を通じてスケジュール管理や勉強法などをお伝えしています。お子様の個性や能力に合わせた個別相談も行なっているので、ぜひお気軽にご相談ください。
聞き手・文:古賀令奈