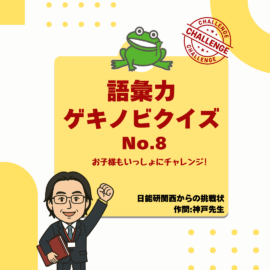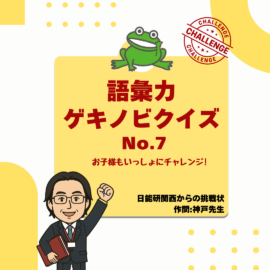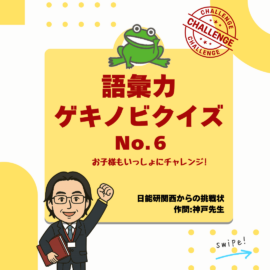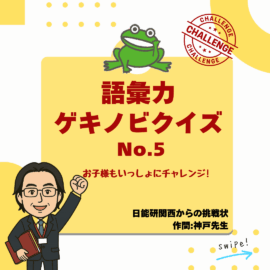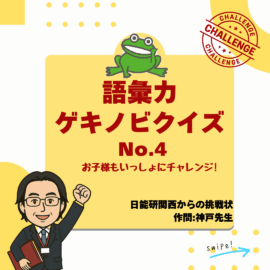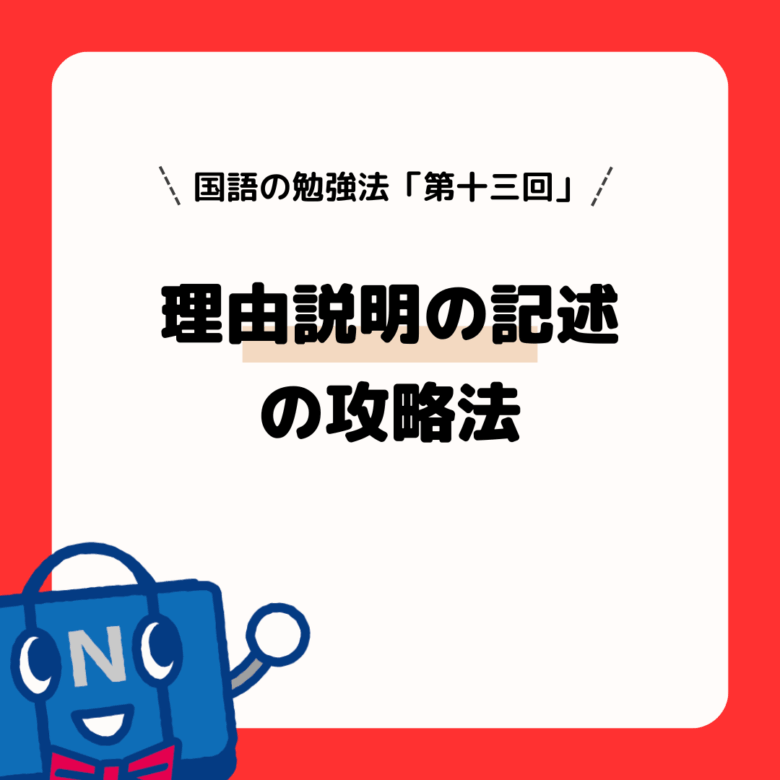
今回は説明・論説文における理由説明の記述の考え方についてお話しします。
理由説明の記述で大切なことは、設問文を丁寧に読んで、何の理由が問われているのかを正しく理解することです。何の理由が聞かれているのかを意識しないで解答を書いてしまうと、設問の意図とはズレた答案になってしまいます。ですから、まずは正しく設問文を理解することを心がけてください。
理由説明の記述問題を考えるときの基本は、傍線の前後から、理由が書かれているところを探し出すようにすることです。その際、理由を表す言葉に注意を払いましょう。たとえば、「ので」「から」「ため」という言葉や、「て」「で」という助詞に気をつけて読むとよいでしょう。また、順接の接続詞「だから」「したがって」の直前の部分には理由が書かれていますし、「なぜなら」という理由説明の接続詞の直後にも理由が述べられています。このような理由を見つけるためのサインとなる言葉を見逃さないようにしましょう。
傍線の前後に理由が見つからないときは、傍線を含む文脈を意識して、探す範囲を広げます。このときは文章構成を意識するようにします。設問が作られている傍線を含む抽象的な部分から見て、具体例の部分をはさんだ、ひとつ前、もしくはひとつ後ろの抽象的部分に理由が書かれていることがよくあります。また、傍線中に出てくる言葉と、同じ言葉が使われている部分に理由が書かれていることも多いので、これらに着目して理由が述べられている場所を見つけましょう。
また設問によっては、「本文全体をよく読んで」という指示が入っていることもあります。これは傍線が文章の始めに引かれていて、その理由が書かれている場所が文章の最後にあるときや、逆に、傍線が文章の最後に引かれていて、理由が文章の始めに書かれているときに使われる指示です。こういった設問文のヒントも見落とさないようにしてください。
ここまでは本文中に明確な理由が述べられているものについて見てきましたが、はっきりと理由が述べられていない問題もあります。その場合は、理由を考える際の手がかりとなる「事実」をつかみ、「事実」と傍線部との因果関係を自分で考える必要があります。また、傍線から「なぜ」という質問を繰り返し、「なぜ」という質問がそれ以上出ないところまで、因果関係をさかのぼっていくという手法を使うと解ける問題もあります。
理由説明の記述の難しさは、これまで説明した方法のどれを使えばよいのかということが、すぐに見抜けない点にあります。しかし、これまでに説明してきたことを身につけていれば確実に解けますので、問題練習を通して考え方のコツを身につけていってほしいと思います。
次に、理由説明の記述で気をつけておかなければいけないことを2点お話しします。1つ目は、自分の書いた答案に、「なぜ?」という疑問が生じないかという視点で、見直しをすることです。書いた答案に疑問が生じるようであれば、説明不足の答案になっています。これ以上疑問点が出ないところまで突き詰めて、答案をまとめるようにしてください。2つ目は、自分の書いた答案と傍線部分をつないで読んでみて、理屈が通っているかどうかを確かめることです。理由説明の記述は具体化の記述と違い、傍線部の内容を言いかえて説明してしまうと、間違いになります。ですから、答案の中に傍線部を言いかえた表現を書いてしまわないように気をつけましょう。
今回は説明・論説文における理由説明の記述の考え方を説明しました。理由説明は頻出の設問ですので、しっかりと身につけてほしいところです。物語文における理由説明の考え方は次回説明したいと思いますので、楽しみにしておいてください。