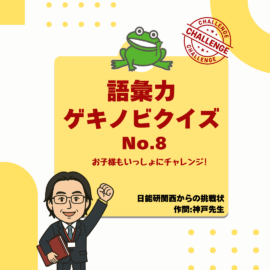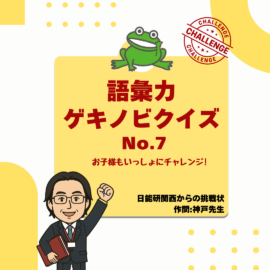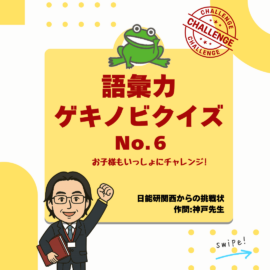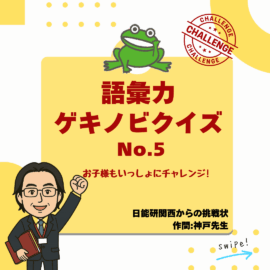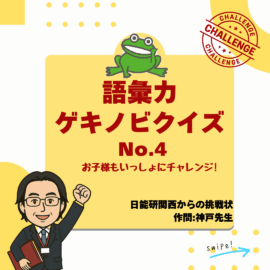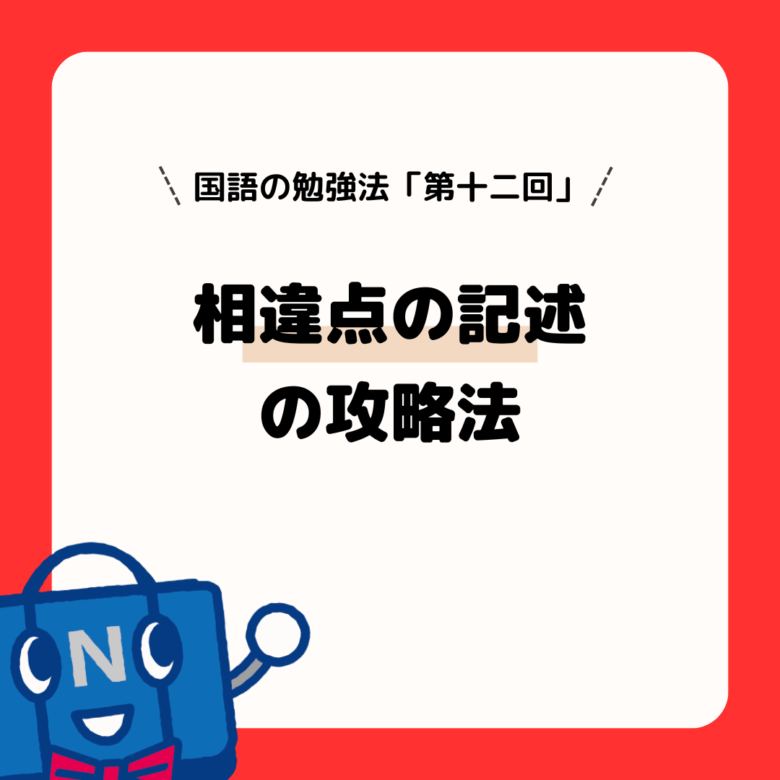
今回は相違点の記述の考え方をお話しします。
説明文や論説文では、ある物事を説明するときに、対照的な事柄と比較しながら文章が書かれることがよくあります。対照的な事柄と比較することで、説明したいことがより明確に伝わりやすくなるという効果があるからです。ですから、文章の中で対比が使われていたら、何と何がどういう点で反対の関係にあるのかを意識して文章を読み進めることが必要です。
相違点を説明させる記述問題では、文章の中で対比されている事柄が、どういう点で対照的なのかを整理して記述する力が求められています。相違点の記述問題を解く際、一番大切なことは、比較の基準を明確にして解答を書くことです。このことを意識せずに解答を書いてしまうと、的外れな解答や、何を伝えたいのかがはっきりしない、ピントのぼやけた解答になってしまいます。
たとえば、Aは丸くて赤いという特徴を持っていて、Bは四角くて白いという特徴を持っているとします。AとBの違いを説明するとき、「Aは丸いのに対して、Bは白いという違い」と説明したとしたら、どうでしょう。何のことだかよくわかりませんね。AとBを整理するとき、形で比較すると、Aは丸く、Bは四角い。色で比較すると、Aは赤く、Bは白い。このようになります。ですから説明するときも、比較の基準を意識して、「Aは丸いのに対して、Bは四角いという違い」とか、「Aは丸くて赤いのに対して、Bは四角くて白いという違い」のように答えなければなりません。ここであげた例は易しい内容なので、こんな間違いをするはずはないと思われるかもしれませんが、文章が抽象的で難しくなってくると、比較の基準がずれた答案が結構見られますので、注意しておきましょう。
比較の基準を明確にしたあとは、それぞれの要素を押さえていくことになりますが、その際は対義語をうまく用いるようにすると、答案をまとめやすくなります。また、AとBが反対の内容だと書かれていても、その具体的な説明がAは書かれていて、Bは書かれていないという文章もあります。そのような問題では、Aの具体的内容を理解した上で、BについてはAを説明する際に用いた言葉の対義語を自分で考えて、答案の中にもりこむようにします。たとえば、Aは積極的な特徴があると書いてあれば、それと対比されるBは「消極的」という言葉を答案に入れるようにします。
ここで記述問題においてよくみられる誤答例について触れておきます。それは、「打ち消しの言葉を使って答案をまとめてはいけない」ということです。たとえば、AとBが対比されている文章で、Aの特徴として「明るい」という内容が書かれているとします。このとき、Bの内容をわかりやすく説明することが求められたとします。そのとき、「Bは明るくない」のように、Aの特徴を打ち消して解答をまとめてしまうと、不正解になります。「Bは暗い」とBの特徴を正面から説明しなければ、正解の答案とは認められません。ここで説明した誤答は、相違点の記述にだけ見られるものではなく、具体化の記述にも見られる誤答ですので、よく注意するようにしてください。
説明するべき要素を押さえることができたら、それを答案にまとめていきます。答案をまとめるときは、「Aは〜なのに対して、Bは〜である。」という形式で書くようしましょう。
相違点の記述問題の出題頻度はそれほど高くありませんが、スッキリしたわかりやすい答案が書ける人とそうでない人で、かなり差が出る設問です。ですから、しっかりと書き方を身につけてほしいと思います。