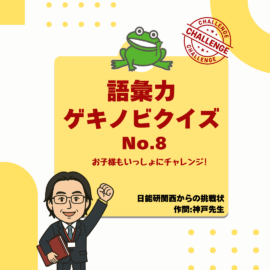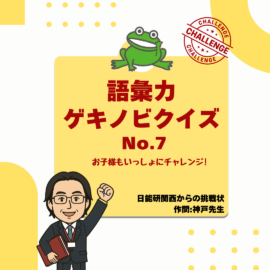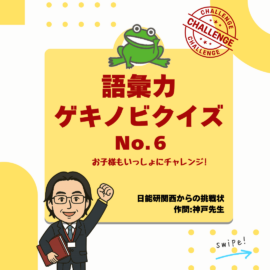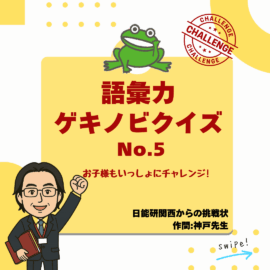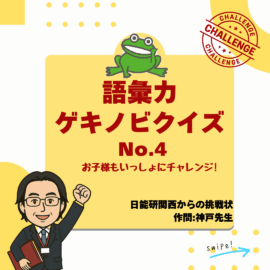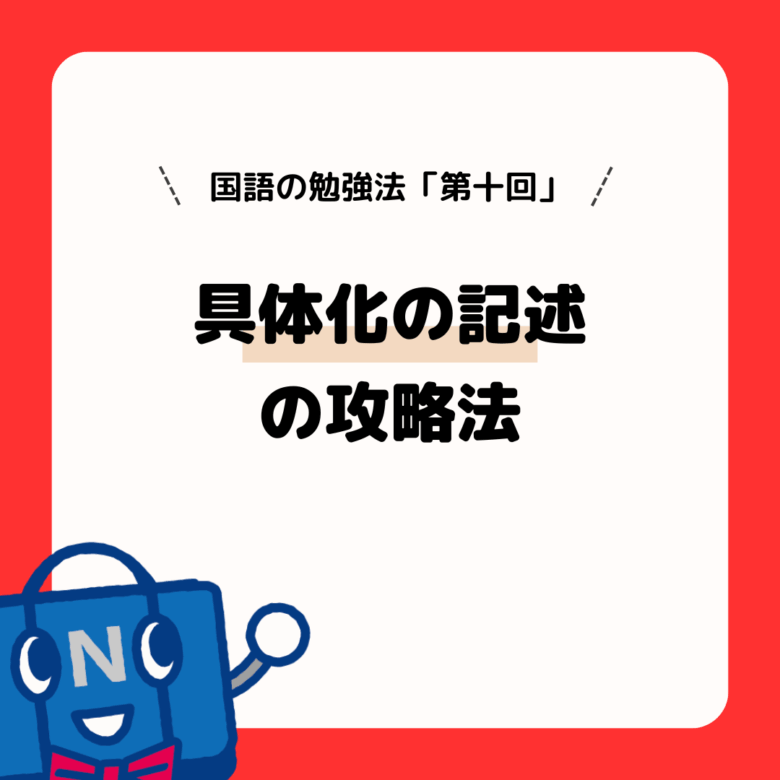
今回からは、記述式問題について、設問パターン別に攻略法を説明していきます。今回は具体化の記述について見ていきたいと思います。
具体化の記述とは、傍線部の内容をわかりやすく説明する問題で、「~とありますが、どういうことですか、説明しなさい」という形で聞かれる、記述式問題です。入試問題でよく出題される設問の1つです。
具体化の記述を解くときに、初めに行うことは、作問者が傍線部中のどの部分の説明を求めているかを考えることです。このことを意識せずに答案を作成すると、ピントのぼやけた説明になってしまいますので、注意しましょう。説明が求められている部分は、傍線の中に1ケ所とは限りませんので、この点にも注意をはらってください。
説明が求められている部分をおさえられたら、その部分の内容について、詳しく説明している文中の箇所を探していきます。では、どのようにして探せばいいのでしょうか。詳しく説明している箇所を見つけるためによく使う技を紹介したいと思います。
1つ目は、傍線部中に使われている言葉の意味やニュアンスを考え、本文の内容と重ねていくという方法です。たとえば、「『そのような返事をする人は脈がある』とありますが、『脈がある』とは、どういうことですか、説明しなさい」と問題が出題されたとします。この問題では、「そのような返事」という部分と、「脈がある」の部分の説明が求められていることをおさえます。この「脈がある」の内容を説明するときに、言葉の意味を考えてみます。「脈がある」は、「見込みがある」とか、「可能性がある」という意味です。そこで、文中では何の見込みがあると書かれていたのかを考えます。このようにすれば、傍線の内容を説明している文中の箇所を、素早く見つけられるようになります。
2つ目は、傍線部中の言葉と同じ言葉、似た意味の言葉が使われている箇所を探すという方法です。この同一語句が繰り返し使われているところが、傍線の内容を説明している箇所になっていることがよくあります。
このようにして、傍線部の内容が説明されている文中の箇所が見つかったら、最後はその見つかった部分の内容を、傍線部の表現と置き換えて言いかえるようにします。このとき、傍線部中の説明が求められている箇所以外の表現も、できるだけ別の言葉で言いかえるようにすると、上手な説明になります。
今回は具体化の記述の解き方を説明しました。出題頻度の高い設問ですので、しっかりとマスターしたいですね。