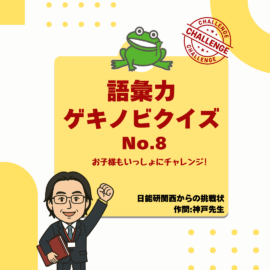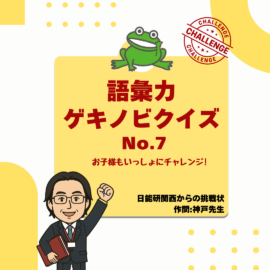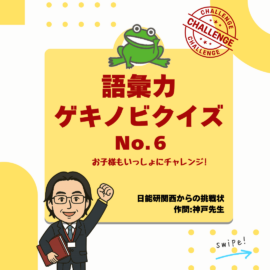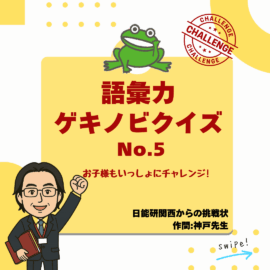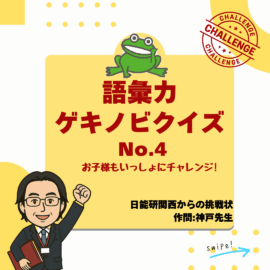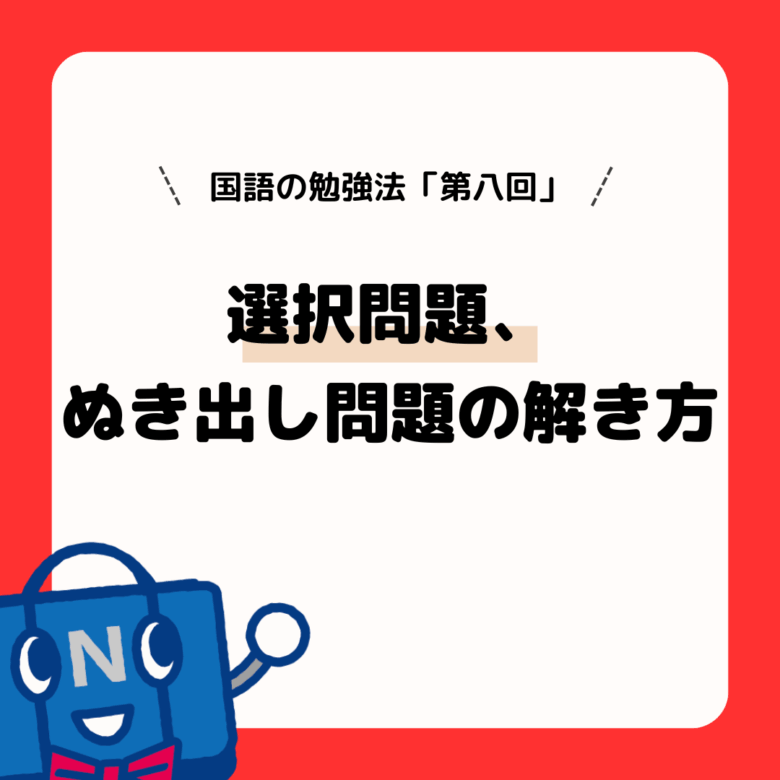
今回は選択問題、ぬき出し問題の解き方についてお話します。読解問題の中でも選択問題は出題の比率が高く、正答率を高めることは中学入試を突破するうえで重要になります。また、ぬき出し問題は正解の箇所を見つけるのに時間がかかる場合もあり、限られた時間の中で解かなければならない入試において、その処理の仕方がポイントとなります。
まず、選択問題の解き方から説明します。選択問題に関する相談で一番多いのは、「選択肢を2つにしぼるところまではいけるのだが、いつも誤りの方を選んでしまう」というものです。これは選択問題を消去法で解こうとしているので起こる問題だと言えます。消去法を使って解くことが絶対によくないというわけではないのですが、実は消去法では解くことができない問題もあるのです。それは、説明しなければならないポイントが複数ある問題です。たとえばAとBの2つの内容を説明しないといけない問題で、Aの内容しか書いていない選択肢、Bの内容しか書いていない選択肢、AとBの両方の内容を書いている選択肢があったとします。もちろん正解はAとBの両方の内容が説明されている選択肢ということになりますが、消去法で解こうとすると、この3つの選択肢はどれも消せません。なぜなら、どの選択肢の内容にも誤りがないからです。このように消去法は完璧な解法ではないのです。
得てして選択肢問題が苦手な生徒は、消去法、つまり選択肢に頼って問題を解こうとしているので、その姿勢を改めることが選択問題の正答率を上げる鍵になります。
もちろん、消去法で解くのが非常に有効な問題もあります。それは、本文に傍線が引かれていないタイプの問題です。たとえば、本文の内容と一致する選択肢を選ぶ問題では、選択肢に書かれている内容を本文の内容と照合させ、選択肢のどこが誤りなのかをおさえるようにします。
では、選択問題を解く際には、どのようなスタンスが必要なのでしょうか。それは、設問文を読んだ後、そのまま続けて選択肢に目を通すのではなく、前回説明した読解問題を解くときの4つの方法を使って、まず頭の中で解答を想定します。そしてその想定した解答と一致する選択肢を選ぶようにします。もちろん、解答を想定してから選択肢を見ても、2つの選択肢で迷うことはあります。そのときは、2つの選択肢の説明の違いがどこにあるのかを分析してください。そしてその違いを意識しながらもう一度本文を確認し、どちらが正しいかを検討するようにします。このようにすれば、選択問題での誤答を減らすことができるでしょう。
続いて、ぬき出し問題の解き方を説明したいと思います。設問を解く際の基本的な考え方は選択問題と同じです。設問文を読んで、解答を頭の中で作成します。そして、解答として想定した内容が書かれている部分を文中から探すようにします。
しかし、この探すという作業が厄介で、これがぬき出し問題を難しくしている要因なのです。なぜ厄介かというと、解答の場所がある程度限定できる問題と、そうではない問題があるからです。本文を読んだときに本文全体の構成を正しく理解していれば、どこにどのような内容が書かれているかが分かっているため、探す部分に目星がつけられます。逆に言えば、本文の内容、本文の論理展開が正しく理解できていない場合は、探す箇所を限定できず、本文を最初から最後までもう一度読み直し、探すしかないことになります。また、問題によっては、本文全体からやみくもに探さざるを得ないものもありますし、傍線の内容とは全く脈絡のない部分に解答があるという作問がなされることもあります。
したがって、ぬき出し問題では、その設問に手を出さないというのも戦略の1つになります。つまり、解答が想定できても、ぬき出す場所がすぐに見つからないときは、いったんその設問はパスした方がよいと言えます。
次に、字数制限のあるぬき出し問題の解き方、注意するべき点について説明します。ぬき出し問題の字数制限は、5文字単位で考えます。たとえば、30字以内でぬき出す問題だと、解答の文字数は26字から30字の間になります。また、長い字数設定の問題では、設問が作られている傍線部分の表現に対応させて、ぬき出す部分の「終わり」を先に見つけるようにしてください。そして、下から上に字数を数えるようにします。ぬき出しの「始め」の部分を先に見つけようとすると、設定字数に合わないときは、また初めから数え直すことになってしまい、時間を浪費することになります。「終わり」を先に探せば一回数えるだけで解答の場所を確定できるので、時間の短縮につながります。
次回は記述式問題の解き方について説明しますので、ご期待ください。