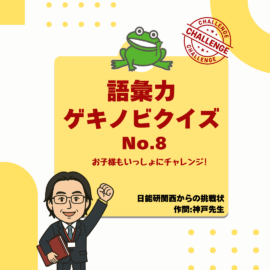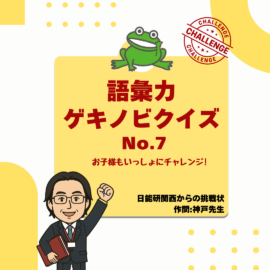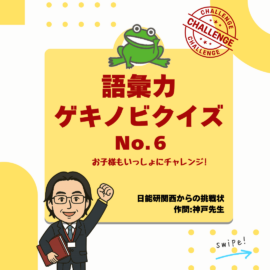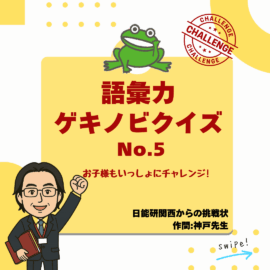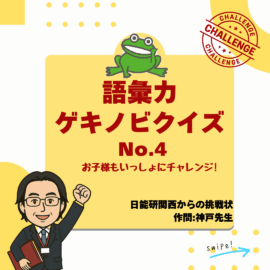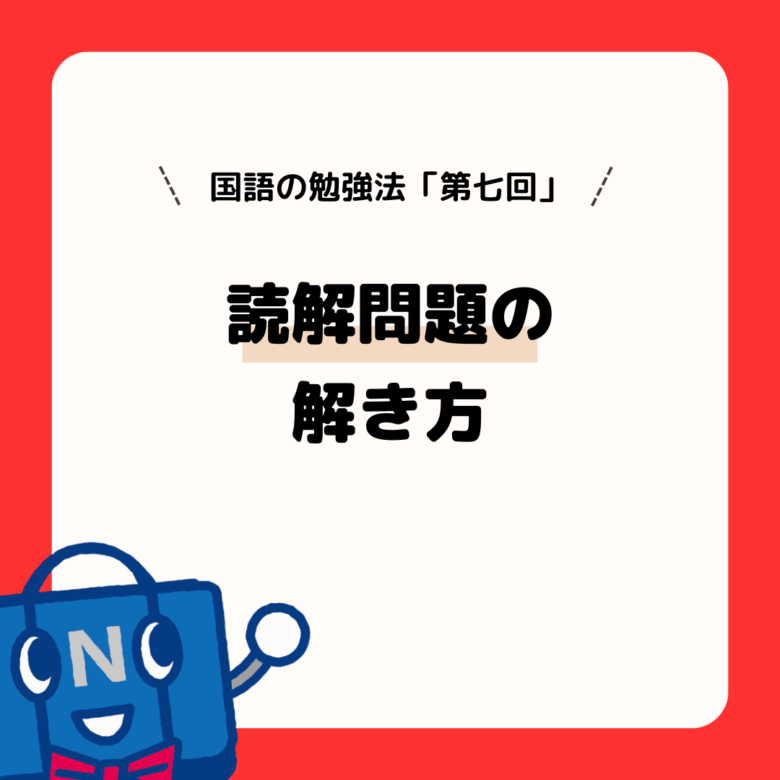
今回は読解問題の解き方についてお話します。文章の内容を正しく理解できたかどうかをたずねる読解問題には、選択肢の中から正しいものを選んで答えるもの、文中から解答の箇所をぬき出して答えるもの、記述式で答えるものの、三つの形式があります。この三つの形式には、それぞれ解答を導くために知っておくべき技法があります。三つの出題形式において身につけておくべきテクニックについては、次回以降詳しく見ていきます。今回は、どの設問形式であっても共通して行う、読解問題を解く上での基本となる作業について説明していきます。
読解問題を解く上で一番大切なことは、出題者が何を答えさせたいのかを読み取ることです。設問の意図を正しく理解できていなければ、正しい答えにはたどり着けません。ですから、設問文はじっくりと、分析しながら読むように心がけましょう。たとえば、傍線部の内容を理解できているかどうかを説明させる問題では、傍線部中のどの部分の説明が求められているかを意識できているかが、問題を正しく解くカギになります。理由を聞いている問題では、何の理由が聞かれているかを意識して問題を解くようにしなければ、間違えた答えを選んだり、書いたりしてしまいます。
設問の意図が正しく理解できたら、解答の手がかりとなる部分を文中から探します。ここからは、この解答の根拠をおさえるための方法を説明していきたいと思います。
読解問題の大半は文中に傍線が引かれていて、その傍線部の内容に対して設問が作られています。このような傍線が引かれている問題を解くときに最初に行ってほしいのは、傍線を含む一文を読むことです。そして、次の4つの方法で解答の根拠を探すようにします。
①傍線を含む一文の中に、指示語、接続語が使われていないかをチェックする。
傍線を含む一文の中に指示語があれば、その指示語が指している内容を読み取ることで、解答が得られるパターンが大半です。傍線を含む一文の、次の一文の初めに指示語があるパターンもあり、これは傍線の次の一文が解答の手がかりとなります。また、接続語がある場合は、その接続語の働きに注目すると答えがわかるものがほとんどです。たとえば、傍線を含む一文が、「しかし」という逆接の接続詞で始まっているのであれば、傍線部とその前の一文とが反対の関係になっているので、対比関係に留意して設問を解きます。
②傍線を含む一文の、文構造を考える。
主語に傍線が引かれているときは述語の部分が、述語に傍線が引かれているときは主語の部分が、解答の手がかりになることがよくあります。また、傍線部が修飾している言葉や、傍線部を修飾している言葉に注目することも大切です。
③傍線を含む一文の中に使われている言葉の意味に着目する。
これは傍線部の内容を正しく理解できているかどうかを問う問題でよく使う技です。傍線を含む一文の中で使われている言葉の辞書的意味を考え、それが今解いている問題文ではどいうことに当たるのか、照合させるようにします。
④傍線を含む一文に含まれるキーワードに着目し、そのキーワードが用いられている文中の別の箇所を探す。
傍線の前後に解答の手がかりがない場合、傍線部中のキーワードに注目し、同じ言葉が使われている文中の別の箇所を探すようにします。そうすると、傍線の内容を言いかえて説明している部分を見つけることができます。その部分をふまえて解答を考えるようにします。
以上の4つが解答の根拠となる部分を見つけるための、読解の基本作業になります。この基本作業をふまえた上で、選択問題、ぬき出し問題、記述式問題の解法を細かく説明していきたいと思います。次回は、選択問題、ぬき出し問題の解法をお話ししますので、ご期待ください。