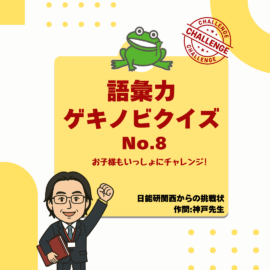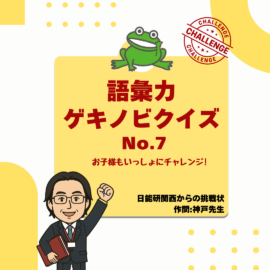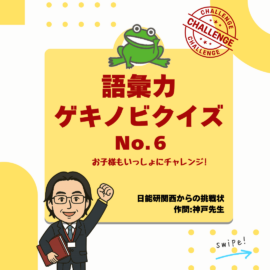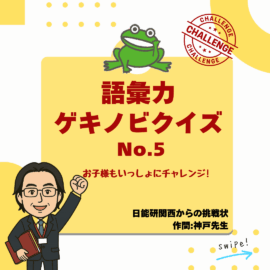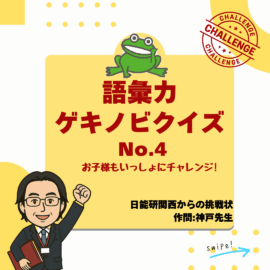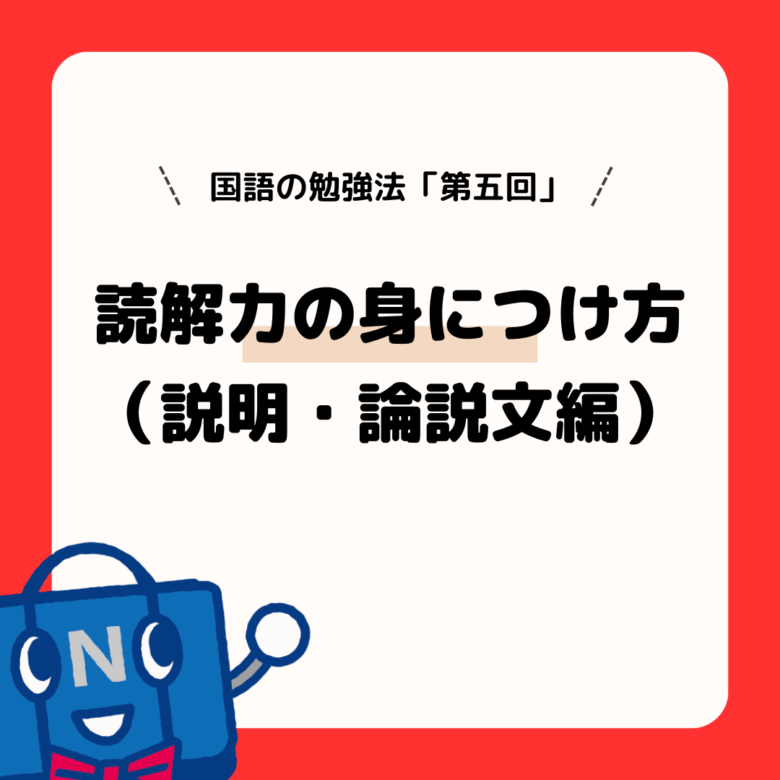
今回は説明文、論説文の読解力を身につけるための学習方法についてお話しします。
説明文、論説文の読解においては、細部を正確に読み取る力と、文章全体の内容を大きくとらえる力が求められます。文章はいくつかの形式段落を積み重ねていくことで成り立っています。ですから、それぞれの形式段落に書かれている細部の内容を正確に理解することが必要です。しかし、細部にばかり気をとられていては、筆者がその文章を通して何を言いたかったのかがすっきりと頭に入ってきません。国語が苦手な人は、どうしても今自分が読んでいる部分の内容を理解することだけに意識が向いてしまい、本文全体の中で今読んでいる部分がどのような働きをしているのかについて考えることが、おろそかになってしまいがちです。その結果、文章を最後まで読んでも、文章の見取り図が描けていないため、内容が頭に残らないという状態になりがちです。
では初めに、細部を正確に読み取る方法から説明していきたいと思います。
文章は、筆者の考えや、これから説明する内容やこれまでに説明してきた内容をまとめている抽象的な部分と、例やたとえを用いて説明している具体的な部分から成り立っています。当然、抽象的に書かれている部分に大切な内容が書かれているので、まず文章の中から抽象的に書かれている部分を見つけられる力を身につけることが大切です。しかし、抽象的な部分が大切だと言っても、具体的な説明の部分が必要ないわけではありません。抽象的に書かれているところは、書いてある内容が難しかったり、一読しただけではわかりにくかったりするものです。ですから、具体例やたとえの部分を補完的に読むことで、抽象的部分がどういうことを言っているのかを理解するように心がけてください。
次に、抽象的に書かれている部分を見つける方法を4つ説明していきたいと思います。
①キーワードが入っている文に注目する。
文章の中で何度も繰り返し使われている言葉や、話題に関連する言葉の入っている文をおさえるようにします。
②強調表現が使われている文に注目する。
「〜しなければならない」「〜するべきだと思う」などのように、強調する表現が使われている文をおさえましょう。
③接続語に注意する。
「だから」「したがって」などの順接の接続語の後ろ、「しかし」「ところが」などの逆接の接続語の後ろ、「つまり」「このように」などのこれまでの内容をまとめたり、言い換えて説明したりする働きをする接続語の後ろは、注意して読むように心がけましょう。具体例をあげて説明する接続語「たとえば」は、「たとえば」の前に抽象的な内容が書かれています。
④各形式段落の初めの一文と終わりの一文に注目する。
日本語の文章では初めと終わりに大切な内容が書かれることが多いので、各形式段落の初めと終わりは注意して読んでください。文章全体で言えば、初めの形式段落と最後の形式段落が大切な段落と言えます。
基本的には抽象的な部分と具体的な部分は交互に出てきますので、どこで入れ替わるかに注意しながら読み進めるようにしてください。また、重要な文に線を引きながら読むようにするとよいでしょう。
続いて、文章全体の構成を考えながら本文を読めるようになる力の身につけ方について3つ説明します。
①序論、本論、結論という大きな枠組みを意識してみる。
初めの段落ではその文章の話題が提示され(序論)、その後、例や理由をあげながら、話題に対しての具体的な説明があり(本論)、最後の段落でその文章を通して伝えたいことを述べる(結論)という形式の文章が、中学入試で出題される問題では多く見られます。
②これから書かれるであろう内容を予測しながら文章を読むようにする。
たとえば、「どうしてそう言えるのだろうか」のように、疑問文が出てくれば、その答えとなる内容が筆者の主張となっていることが大半なので、疑問文が出てきたら、その答えがどこで説明されるかを意識しながら文章を読むようにします。また、「初めに」「まず」「さらに」「しかも」「また」「〜だけでなく」などの言葉が出てくれば、どのような内容と、どのような内容が並列されているのかに注意しながら読み進める必要があります。また具体例の部分は、何の例を説明している箇所なのかを念頭におきながら読むことが重要です。
③文章の論理展開を追いかける。
論説文では、話題となることがらに対して、例をあげることで読者の理解を深めたり、主張に対する理由を説明したりしながら、文章を結論へと導いていきます。入試問題で高得点を取れるようになるには、細部を読みながら、同時に文章全体の大きな流れをつかむことができるようになることが必須です。文章の論理展開を理解しながら細部を読めるようになる練習方法を紹介します。それは、形式段落をひとつ読むごとに一度読むのを止めます。そしてその形式段落の内容を、抽象的に書かれている部分に着目して頭の中でまとめてください。まとめることができたら、次の形式段落を読み、同じようにその段落の内容をまとめます。次に今読んだ形式段落の内容と、一つ前の形式段落の内容の関係を考えるようにしてください。同じ内容が続いているのか、前の段落の具体例があげられているのか、前の段落に書かれたことの理由が述べられているのかなどを意識して考えてみましょう。これを繰り返して文章を終わりまで読みます。そして最後に、その文章は何について書かれていて、どのようなことを筆者が言いたかったのかについて、必ず考えるようにしましょう。
ここで説明したことはとても難度の高いことですが、文章構成という見取り図を頭の中に描きながら細部が読めるようになると、より正確に文章を理解することができるようになります。また、文中のどの部分にどんな内容が書かれていたのかを意識できていますので、設問を解く力も上がっていきます。
次回は、物語文の読解力を身につけるための学習方法についてお話ししますので、次回もご期待ください。