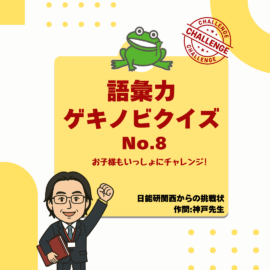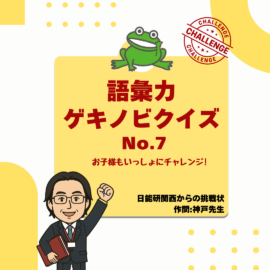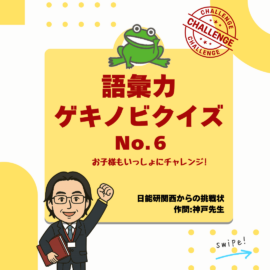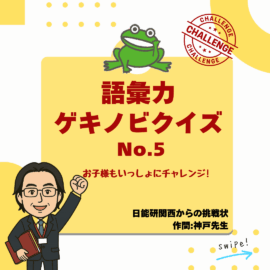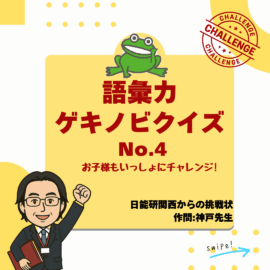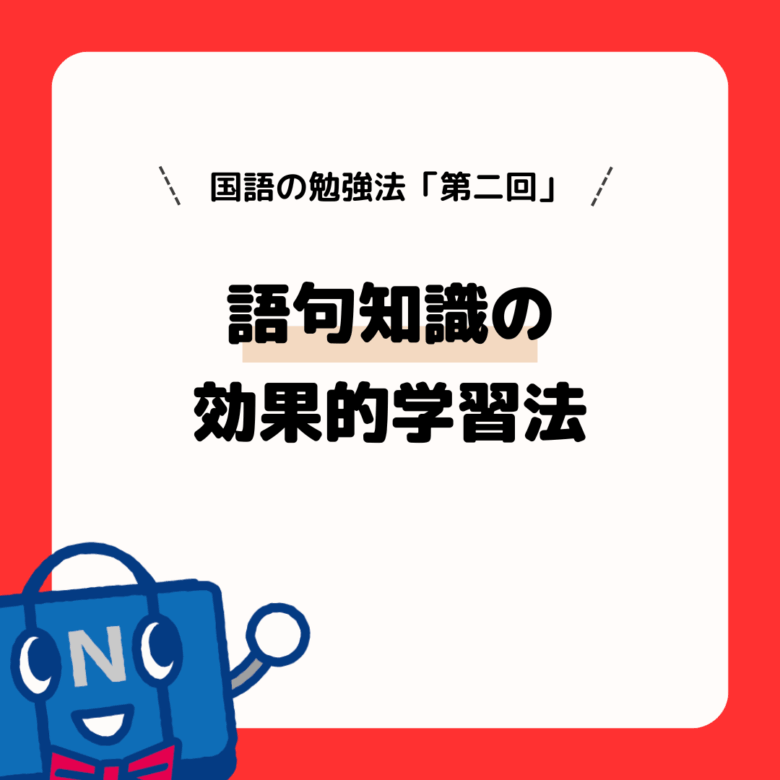
前回は、中学入試において求められる国語力についてお話ししました。その中で、すべての出発点が言葉の知識にあることを説明しました。
その言葉の知識は、大きく二つに分けられます。一つは、ことわざ、慣用句、四字熟語といった、いわゆる知識問題として入試で問われるものです。もう一つは、文章を読解するときに必要となる一般的な語彙力です。今回は、知識問題として問われる語句の効果的な学習方法についてお話ししたいと思います。
中学入試の語句問題では、ことわざ、慣用句、四字熟語、外来語などの幅広い知識が問われます。
初めに、ことわざ、慣用句、四字熟語の学習方法について、説明したいと思います。ことわざ、慣用句、四字熟語の学習では、次に上げる三つのことを意識しておきましょう。一つ目は、言葉そのものを正確に書けること。二つ目は、その言葉の意味を正確に覚えること。三つ目は、その言葉が使われるシチュエーションを理解していること。この三つが揃っていないと、確実に得点を取ることはできません。また、意味を見て、その意味を持つことわざ、慣用句、四字熟語が言えるレベルに到達していないと、実際に身についたとは言えません。
では、数多くあることわざ、慣用句、四字熟語をどうすれば効率的に身につけることができるのでしょうか。初歩的な段階では、漫画やイラストを用いて、ことわざ、慣用句、四字熟語を説明している本を利用するとよいでしょう。学習系漫画は、その言葉の使い方を覚えるにはうってつけです。もちろん、掲載されている言葉の数が少ないという面はありますが、最初の段階ではそれで十分です。まずは限られた数の言葉を、何度も見返すことによって、確実に覚えることが大切です。基本となることわざ、慣用句、四字熟語が身につけば、次のステップへ移行することができるからです。
次のステップでは、一つの言葉を覚えて終わりにせず、その言葉と関連する言葉も一緒に覚えるようにします。この段階で、一気に言葉の知識が広がります。まず、似た意味を持つ言葉や、反対の意味を持つ言葉を合わせて覚えるようにします。たとえば、「蛙の子は蛙」ということわざを覚えるときに、似た意味の「瓜の蔓に茄子はならぬ」という言葉と、反対の意味の「鳶が鷹を生む」という言葉を一緒に覚えるというぐあいです。次に、せっかく「蛙」という言葉を使ったことわざを覚えたのですから、他にも「蛙」という言葉を使ったことわざがないかを調べてみるようにします。「蛙の面に水」や「井の中の蛙大海を知らず」という言葉も合わせて覚えることができれば、一つの言葉から、四つ五つと知っている言葉を増やしていくことができるのです。
また、ことわざ、慣用句では、動物名や植物名の入った言葉、色を表す漢字の入った言葉、体の一部を表す漢字の入った言葉など、あるテーマでくくった言葉をまとめて覚えるようにするとよいでしょう。四字熟語であれば、「一期一会」や「三寒四温」のように漢数字の入ったもの、「自業自得」や「適材適所」のように同じ漢字が二度使われているもの、「右往左往」や「南船北馬」のように対になる漢字が入ったものが、よく狙われます。
さて、ここで大切なことを付け加えておきます。それは、できるだけ自分で辞書を使って調べ、楽しみながら学習することです。調べるという作業をすることで、頭の中に印象が残り、言葉が定着しやすくなります。
次に外来語の学習方法についてお話しします。中学入試では、日常生活の中でよく耳にする外来語が出題されます。ニュースの中で使われている外来語、街の中にあふれる広告や看板などに使われている外来語などに、意識をむけてみましょう。目にした知らない言葉をそのままスルーしてしまわず、辞書で調べてみる。たったこれだけのことで、ずいぶん外来語は身につくはずです。
カラーバス効果という言葉をご存知でしょうか。ある一つのことを意識することで、それに関する情報が無意識に自分の手元にたくさん集まるようになる現象のことをいいます。今日は街で見かけるものの中から外来語を五つ見つけてみようとか、「ア」から始まる外来語を探してみようとか、家から出かけるときにそう意識するだけで、知っている外来語の数は、格段に増えていきます。
また、辞書を使って学習する方法としては、同じ音で終わる外来語をまとめて覚えるやり方がおすすめです。電子辞書やスマートフォンの辞書アプリで、「逆引き」という機能を利用します。たとえば、「逆引き」で「ション」と入力すれば、「テンション」「パッション」「ローテーション」など、「ション」で終わる外来語が表示されます。それらをまとめて覚えるようにするのです。
今回は、ことわざ、慣用句、四字熟語、外来語を身につけるための具体的な学習方法について説明しました。ぜひ実践してみてください。次回は、文章読解で必要になる語彙力を増やす方法についてお話ししたいと思います。